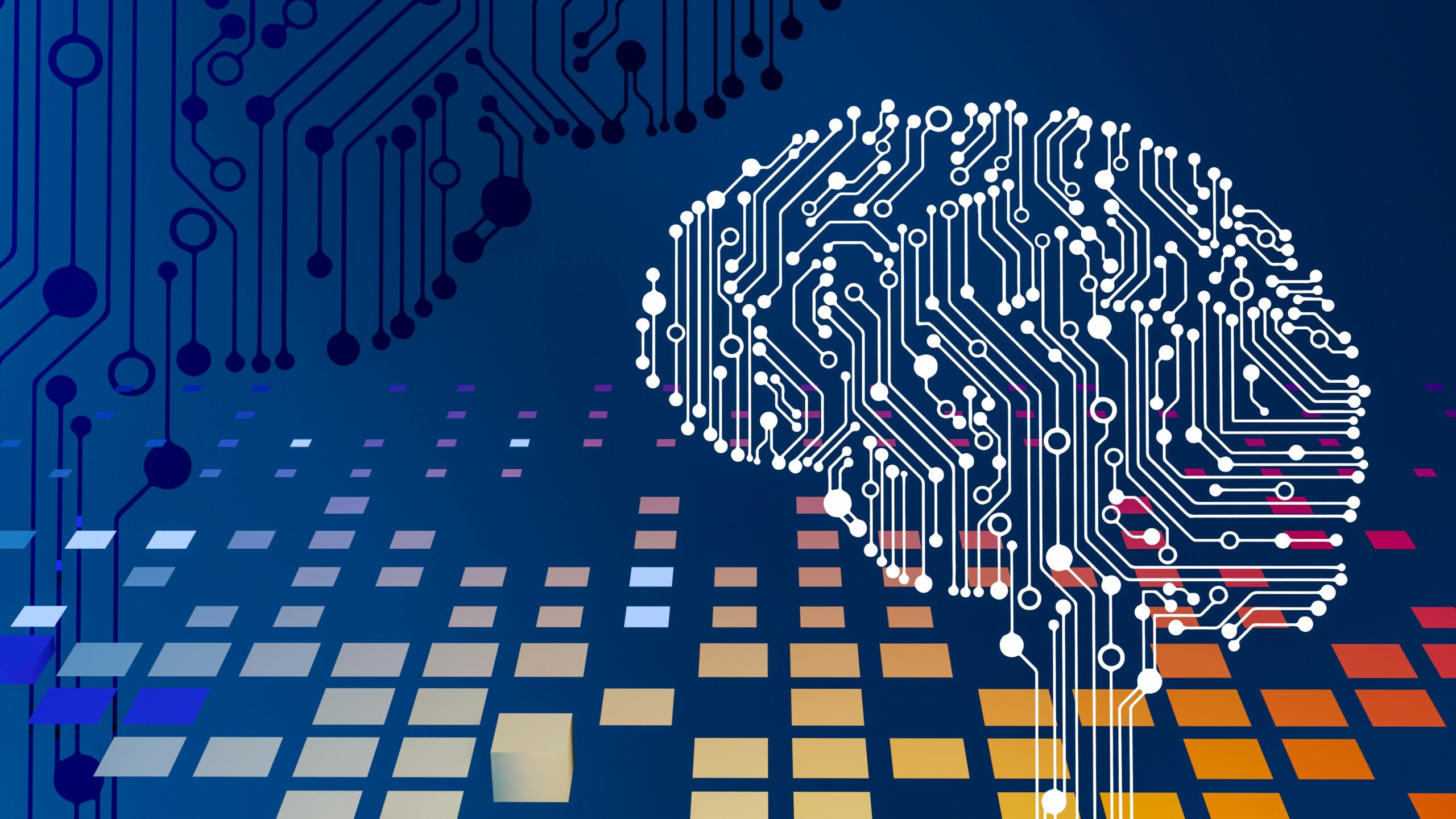IT人材不足の原因は?現状と企業がすべき対応
テクノロジーが急速に進化し、社会のあらゆる面でITスキルの重要性が増加する中、企業が直面している最大の課題の一つが、IT人材の不足です。間もなくAIやIoTなどの技術がさらに普及することを考えると、この問題は今後ますます深刻化することでしょう。
それでは、IT人材不足はなぜ起きているのでしょうか?また、企業がこの課題にどのように対応すべきなのでしょうか?
本記事では、IT人材不足の原因と現状、そして企業が取り組むべき対応策について掘り下げていきます。

IT業界の人材不足とは
ITの進化は驚異的で、IT業界だけでなく、製品やサービスの開発にも影響を及ぼしています。かつてはITベンダーが中心だったシステム開発も、近年では外部委託ではなく自社で直接担当するIT関連の職を創設する企業が増えています。
さらに、デジタルトランスフォーメーション(DX)を進行させる企業の増加に伴い、DXのリーダーシップを執るリーダーやデジタル技術を利用して業務を改善、あるいは新しい事業を創出する役割を担うIT人材の需要が急激に高まっています。この現象は、IT人材不足という問題を一層深刻化させています。
では、どのようなスキルを持つIT人材が不足しているのか、その数はどれくらいなのか、IT人材不足の理由、そしてこの問題の解決策について詳しく解説します。

経済産業省「IT人材需給に関する調査」
経済産業省の「IT人材需給に関する調査」により、IT人材不足の深刻さが示されています。2018年を基準に、2030年までの予測では、IT人材が年々不足していくとの結論が出されました。この不足は経済全体に影響を及ぼし、企業のデジタル化や働き方改革の進展、さらにはAIやIoTなどの最新テクノロジーの導入にも支障をきたす可能性があります。
不足予測は高位(約9~3%)・中位(約5~2%)・低位(1%)の3つの成長率別シナリオで試算され、もし最も拡大する高位のシナリオに沿った場合、なんと2030年には最大約79万人ものIT人材が不足することが予想されています。
調査結果から明らかになったこの需給ギャップは、問題解決が遅れると企業の革新や生産性向上を阻害するリスクがあります。
それだけに、IT人材の育成および確保は待ったなしの課題と言えます。産学連携などを活用し、即戦力となる人材の育成に重点を置くべきです。
この調査結果は、今後のIT人材育成策や対策を検討する参考になるもので、その現実的な状況の把握に役立ちます。

IT人材の不足理由とは
IT人材の不足理由を詳しく見ていきましょう。

IT需要の拡大
情報技術(IT)の急速な発展は社会をデジタル化する流れを加速させており、大企業から中小企業までがITによる業務効率化や新規ビジネス構築に取り組む動きが広がっています。
特に、AIやIoTなどの革新的なテクノロジーの進展は、個別のビジネス分野だけでなく、全体のビジネスパラダイムに新たな課題を生み出しており、これに対応するためには高度なITスキルを持つ人材の需要が増大しています。
加えて、コロナウイルスの影響によるテレワークやオンライン会議の普及は、IT技術への依存度を一層高める結果となり、企業内でのセキュリティ対策やソフトウェア開発、データ分析といった幅広いITスキルを有する人材が不可欠となっています。
しかしこの一方で、教育制度や研修システムの現状は、これらのIT需要に対する人材供給を十分に保障する体制を整えられていないのが実情です。
この問題を解決するためには、教育制度の改革や企業内研修の強化が求められ、今後もIT人材供給の安定化に向けた課題改善が必要となるでしょう。

労働人口の減少
日本の情報技術(IT)業界は、継続的な労働力不足に直面しています。
この問題の根底には、日本の労働力人口の減少が深く関与していると言えます。
少子高齢化が進んでいる日本では、労働力人口が次々と減少している状況が現れています。
この影響は、革新的なアイデアと新鮮な視点を求め、高度な技術と知識を必要とするIT業界に特に顕著です。したがって、供給可能なIT労働力が不足してしまうという問題が発生しています。
さらに、IT業界は絶えず進化し続けている性質を持っているため、新技術を学び続ける能力が求められます。
しかし、労働力人口の減少により、人々が新たな技術を習得する時間も短縮されてしまっています。その結果、新たな技術の習得を可能にする労働力さえも不足しているという難問が生じています。
さらに問題を難しくするのが、労働人口の減少が引き起こす人件費の高騰です。これが結果として企業の教育投資や研修費用に変化をもたらし、教育制度や労働環境にも影響を及ぼしています。
このように、IT産業の労働力不足は、単なる人口減少という問題だけではなく、より多角的な観点から考えるべき課題となっているのです。
IT技術の進展
経済産業省の「IT人材需給に関する調査」では、IT専門家を旧来のIT専門家と最新の先端IT専門家に区分し、その需要と供給の予測を行っています。
その結果、旧来型のITスペシャリストは時間とともに供給が需要を超えるとされる一方で、先端のIT専門家は増加する需要に供給が追いつかない可能性が示されています。
先端IT専門家とは、AI、IoT、ビッグデータなど、第4次産業革命についての広範な知識と技術を持ち、新たな価値創造や効率的な業務運営に寄与する人材とされています。
今後の社会進展に伴い、この先端IT専門家の需要はさらに加速することが予見されます。

需要の高まりが見込まれるIT職種とは
ITには多くの職種があります。特に需要があると言われている職種をご紹介します。
セキュリティエンジニア
デジタル化の進行に伴う強力な波動の中、企業のビジネス運営や製品やサービスの提供は、ITシステムに大規模に依存するエレメントとなりました。その結果、今日の事業継続の大きな懸念事項の一つはサイバーセキュリティです。この背景から、今後も継続的な需給拡大が予想されているのがセキュリティエンジニアというIT分野の専門職です。
セキュリティエンジニアとは
セキュリティエンジニアは、IT業界における一線級の専門家で、システムやネットワークの守護者とも言えます。彼らはシステムやネットワークの防壁を形成し、潜在的な危険や攻撃から守る責任を担います。
その関門となるのは、脆弱性の探索、監視システムの手配、情報セキュリティポリシーの立案、そしてセキュリティ介入の設計と適用など、高度な技術的知識と実地経験が必要となります。
セキュリティエンジニアは教育指導者の役割も果たします。彼らは組織員がセキュリティのリスクを認識し、セキュリティを意識した遵法行動をするようにするための教育研修も行います。そのため、専門的な技術力だけでなく、優れたコミュニケーション力やリーダーシップも求められるのです。

データサイエンティスト
データが溢れる現代にふさわしく、データを戦略的に活用する力がビジネスの成功を左右する時代となりました。そのために重要なポジションを担うのが、データサイエンティストという職種です。彼らはビッグデータの第一人者として、大量の情報から新たなビジネスチャンスを探し出す役目があります。
このデータサイエンティストの需要は、ビジネスの最適化やAI技術の普及、さらにはビッグデータ利用の需要増大により、今後も一段と伸びると見込まれています。
総務省の2017年版「情報通信白書」によれば、「ビッグデータ利活用元年」に突入した現代。事実、データトラフィックの量は年々増え続けており、これらを軸に世界は動いています。
データサイエンティストとは
データサイエンティストとは、幅広い領域にまたがる知識を活かしてデータを読み解き、ビジネスに役立つ情報や解決方法を導き出す専門家です。統計学から人工知能までを使いこなし、データの海を探検し、その中から有用な情報を見つけ出します。
彼らの仕事は、ビジネス目標に基づく課題の定義、必要なデータの特定と収集、そしてそのデータの解析と利活用に至る一連のフローをカバーします。さらに、そこから得られた洞察をもとにして課題解決のための具体的な提案を行います。
プログラミング能力に加えて、高度な数学的技術を用いてデータを処理・解析する能力が求められます。また、その成果を具体的なビジネスアクションに繋げるためのコミュニケーション力やビジネス視野も重要となります。

プロジェクトマネージャー(PM)
プロジェクトマネージャー(PM)の役割は、企業のITプロジェクトを統括し、効果的に運営することです。この役職は、専門的なIT知識に加えて、コミュニケーションやチーム作りのスキルが求められる多面的な職務です。
現代社会では、ビジネスのデジタル化が進む中、PMの役割が更に重要性を増しています。単なるプロジェクトの管理だけでなく、戦略的な視野を持つ問題解決能力、新たなテクノロジーを理解し活用する能力などが、PMには必要とされています。
プロジェクトマネージャーとは
プロジェクトマネージャーとは、プロジェクトを適切に完遂させるための役職であり、全体のマネジメントから具体的な進行管理まで、幅広い職務をこなします。
具体的には、目標設定、スケジュールや資源の管理、リスク対策、そしてチーム間のコミュニケーション調整など、プロジェクトに関連する全ての要素を監督し、統制します。
そのために必要な能力の一つがリーダーシップで、多種多様なスキルを持つプロフェッショナル達を適切に指導し、最高の業績を発揮させるためのマネジメントスキルや人間関係のスキルが要求されます。
また、プロジェクトマネージャーとは敏腕な問題解決者でもあります。
どのプロジェクトにも予期しない問題が付きものですが、そんな困難を予防し、また発生時には素早く対応することで、プロジェクトをスムーズに進行させます。
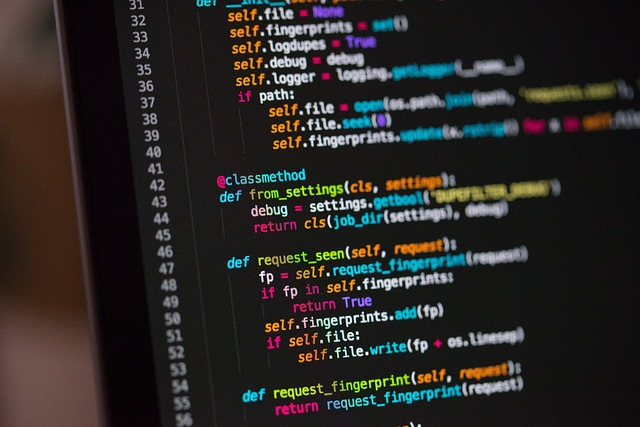
クラウドエンジニア
クラウドエンジニアは、ITインフラのクラウド化を進める多くの企業が求める専門性を持っています。彼らはシステム設計から構築、運用、管理までを担当し、デバイスに依存しないフレキシブルで効率的なビジネス管理を可能にします。
このように、クラウド専門の知識と技術を持つクラウドエンジニアは、業界にとって欠くことのできない存在と言えます。
さらに、クラウドは情報セキュリティと密接な関係があり、適切な運用管理が必須となる分野です。そのため、セキュリティに関する深い理解を持つクラウドエンジニアのニーズは増加の一途をたどっています。
パブリッククラウドの台頭や、企業のクラウド移行に伴って、「オンプレミス回帰」、つまりクラウドからのオンプレミスへの逆転が見られます。しかし、この逆転現象も含め、クラウドエンジニアの需要は減少することはないと考えられます。
クラウドエンジニアとは
クラウドエンジニアとは、専門性や技術力を活かしてクラウド環境を設計、構築する専門家のことを指します。彼らはAWS(Amazon Web Services)、GCP(Google Cloud Platform)、Microsoft Azureなどのパブリッククラウドサービスを使用し、システムの見積もり、運用、保守を行います。
システムが複雑化し、ビジネス環境がリニューアルされる中で、安定したシステム運用を可能にするインフラエンジニアから役割を引き継ぎ、クラウドエンジニアに転向するケースも見られます。クラウドエンジニアは、クラウドだけでなく、オンプレミス環境の設計や構築も可能なマルチタスクなエンジニアとして重要視されています。
また、新しい技術への迅速な対応と丁寧な仕事ぶりが求められる彼らは、新しいクラウドサービスの導入やシステムアップデートの際には、変革への柔軟な対応が求められます。これらのスキルと知識は、ビジネスの進化に伴い、その重要性が増しています。
クラウドエンジニアは、企業のITインフラを背負う重要な存在であり、ハードウェアからソフトウェアまで、幅広い知識と経験を持つ彼らは、今後のビジネス環境の成長と展開を支える重要な力となっています。

IoTエンジニア
近年、IT業界への注目度は高まる一方で、特にIoT(Internet of Things)分野は急速に成長を遂げています。IoTとは、一般的に「物のインターネット」の略称で、様々なデバイスがインターネットを介して繋がり、データを共有し合うことで新たな価値を創出する技術を指します。
スマートホームや工場自動化など、あらゆる分野で活用され始めており、その可能性は無限大と言われています。そして、このIoTの発展を支えているのが「IoTエンジニア」です。彼らは、デバイスの開発からプログラミング、ネットワーク設計など多岐にわたる専門的なスキルを駆使してIoTの実現に取り組んでいます。
IDC Japanのレポートによれば、2021年のIoT市場規模は約5兆8,948億円であるとされ、これが年間平均9.1%の成長率で順調に拡大を続ければ、2026年には約9兆1,181億円にまで達すると予測されています。
IoTエンジニアとは
IoTエンジニアの仕事は、各種デバイスが適切に動作し、収集した情報が適切に伝達・利用されるよう、さまざまなシステムを設計し、管理していくことです。
このために、ハードウェアの設計、セキュリティ対策、データの解析といった幅広い技術が求められます。
IoTエンジニアの特徴的なスキルは、ハードウェアやOS、ネットワーク設計など多岐にわたる知識と技術を持ち、それらを一体化した全体的な構築能力にあります。
また、一人で全てを行うというよりは、それぞれの工程や専門分野に分けてタスクを進め、全体を取りまとめる役割も担っています。

企業がIT人材を確保する方法とは
企業がIT人材を確保するための方法をご紹介します。

採用強化
IT人材を採用するため、企業に求められるのは求人市場の理解と魅力的な働き環境の提供です。求職者のニーズを把握し、それに応えることが一番です。
エンジニアたちは特に、安定した職場環境と自身のスキルアップを重視します。
そのため、企業は単なる利益を得るための場ではなく、彼らは個々のスキルや知識が十分に評価され、スキルを磨く機会が提供される場であると訴えるべきです。
自社の特色や目指すビジョンを明らかにし、それがどのように実現されるのかを示すことで、それが求職者の選択を左右します。
また、どのような経験を積むことができ、どのようなスキルを習得できるのか、また、キャリアの進歩はどのように進行するのかといったキャリアパスを明示し、あるいは教育制度を設けることで、候補者に安心感と期待感を提供できます。
適正な待遇を提示するためにも求職市場の動向を把握し、人材採用に積極的に取り組むべきです。候補者の把握、自社の特徴の強調、教育制度の設立などを通じて、質の良いIT人材を引き寄せることが可能です。

定着率の向上
IT人材を確保する戦略は、単に採用のみに焦点を当てるのではなく、入社した社員が長期間在籍するための「定着」についても考えることが必須です。
入社後の社員定着率を上げるための一つの手法として、企業と応募者間のミスマッチを低減させることが挙げられます。
選考過程では企業は主に自己紹介や応募者のスキルチェックによく力を注ぎますが、スキルマッチだけでなく、企業文化や価値観の合致も重要です。
企業との価値観的な不一致により、新入社員のストレスや不満が高まると、職場での集中力やパフォーマンスが下降し、結果的には離職や転職を希望する傾向になります。従って、企業と応募者間の認識ギャップが少ないことが重要なのです。
ミスマッチを回避するには、採用プロセスで具体的かつ明確な情報を交換し、応募者に対する曖昧な認識を解消することが求められます。
自社の魅力を伝えるだけでなく、応募者のキャリア視野や価値観を深く探り、彼らがどういった組織文化を好むのか、自社との適合性をしっかりと把握することが必要です。
また、具体的な仕事進行法や可能な勤務スタイルなどについても確認することが有効でしょう。

アウトソーシングの活用
派遣やフリーランスなどの形で、業務を外部の専門家に委託することで、企業は必要なITサービスを確保することが可能になります。
自社での人材開発や教育投資などのコストを削ることができるだけでなく、経験豊富な専門家の知識やスキルを活用することで生産性の向上が期待できます。
アウトソーシングにより、企業はIT人材の需要と供給のギャップを埋めることができ、自社の強みや主力業務に集中することも可能になります。
また、外部の専門家から提案される新たな視点やアイデアは、ビジネスの新たな機会を生み出す可能性もあります。
アウトソーシングは、IT人材不足に苦しむ企業にとって新たな選択肢と言えます。より効率的かつ効果的なビジネス運営のために、このオプションを検討してみてはいかがでしょうか。

IT人材育成
IT人材の確保は企業の重要な課題であり、その育成もまた同じくらい重要です。採用だけでなく、社内教育の実施や継続的な教育指導が必要です。
新入社員の教育強化から始め、特にIT分野出身者である新入社員に対しても、企業独自のシステム理解や業務遂行のための研修が求められます。スキルアップの機会を設けることで、社員の成長を後押しすることも大切です。
社内ではITスキルの研修を定期的に開催し、既存社員のスキル向上を目指します。これにより新たな技術導入や業務改進が可能となり、結果として生産性が向上します。
外部研修機関と連携し、各社員のIT技術力を高める施策も有効です。これにより社員は新たな視点や知識を得、自分自身の業務遂行力を高めます。
これらの取り組みを通じ、企業はIT人材の確保だけでなく、育成も同時に行うことができます。社内教育から外部研修まで、トータルに支える体制が重要となります。
具体的には、社員が任意で学習を進められるe-learningを導入することも1つの方法です。
また、社内研修や公開講座の開催、資格取得に伴う賞金提供といった教育システムを作ることで、社員自身の積極性を引き出すことができます。
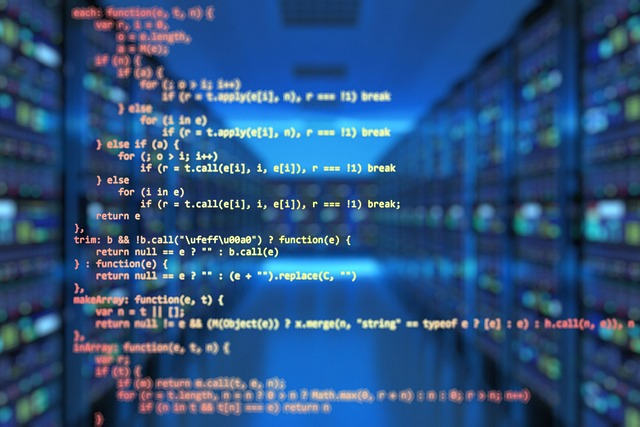
オフショア開発
企業がIT人材を手に入れる策の一つとして考えられるのが、オフショア開発です。このオフショア開発とは、一部あるいは全体のシステムやソフトウェア開発業務を、海外の企業に委託することを指します。
主な利点としては、人件費の抑制が挙げられます。海外、特にITスキルが豊富な国では、日本よりも人件費が低めに設定されているため、予算の範囲内で大量の人材を確保することが可能です。
健全なタイムゾーンを利用することで24時間の作業体制を作り、プロジェクトの進行を加速させることができます。
また、人事配置もフレキシブルに対応可能です。企業の要望に基づいて、必要なスキルを持つスタッフを選ぶことができ、また、必要な時に人員を追加または削減することも可能です。
あくまでオフショア開発は一つの選択肢であり、国や文化の違いがそれほど影響しないプロジェクトや、進捗管理が容易な余裕のあるスケジュールの案件には特に向いています。

まとめ
IT人材不足の原因は教育環境の不備と高度なスキル要求にあり、企業は人材育成に投資し、教育機会を提供することが求められています。
また、雇用形態の多様化や適切な報酬体系を設定することで、魅力的な働きやすい環境を構築し、IT人材不足の解消を目指すべきです。