
定量調査と定性調査の違いとは?特徴や使い分けについて解説
データの分析と理解が重要な要素となる現在、調査手法の知識はビジネスパーソンの必要不可欠なスキルとなっています。その中でも、「定量調査」と「定性調査」は、その重要性から頻繁に使われる調査手法となっていますが、これらの具体的な違いや特徴はあまり理解されていないかもしれません。
今回は、定量調査と定性調査の違いと使い分け、メリットデメリットについて解説します。これにより、データの理解を深め、自身の業務に役立てることができます。
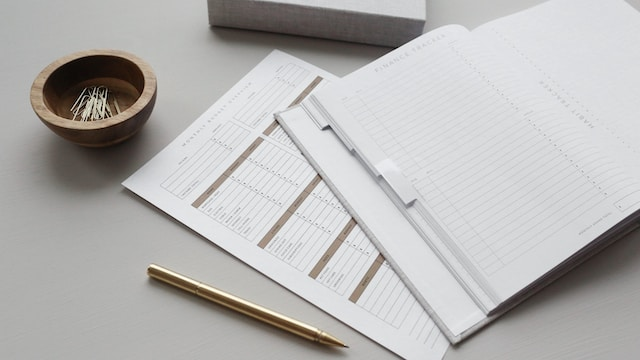
目次
定量調査とは
定量調査とは一般的に統計データの収集と解析を指す調査の一つです。これは具体的な数値やパーセンテージ、頻度等を使用して情報の収集と解析を行う特性を持ちます。通常、市場調査や社会調査、意識調査などで一般的に用いられています。
「定量」という単語自体が示しているように、定量調査は「量」、つまり「数量」を重視します。これは大量のサンプル対象に実行されることが多く、その結果から客観的で再現可能なデータを援出することが可能になります。この手法は、多角的な視点からデータを編集し、比較及び解析を行うため、特定の現象やトレンドを理解する強力なツールとなります。
定量調査の目的は、購入率や製品のイメージ調査などの「実態調査」と、調査者が提唱する「私たちの製品はこのように考えられているのでは?」などの仮説に対する検証、「仮説検証」の二つがあげられます。

定性調査とは
定性調査とは、情報を数量化するのではなく、主観や経験、感情といった「質的な要素」を詳細に調査する研究方法です。
ユーザーが「はい/いいえ」で回答することができない複雑性や変化性を持つデータの収集に最適です。具体的には、個別インタビューやグループディスカッション、参加観察などを通して、対象者の生活習慣や教育環境、交友関係といった背景を掘り下げることが可能です。
対話を通し、対象者自身が認識していなかった潜在的な意見や感情を引き出せるかもしれません。この点が定性調査の魅力であり、人間の心理や行動に深く踏み入った理解を得ることができます。
定性調査は、「人間性」「行動パターン」「価値規範」「関心領域」「習慣」などの核情報を明らかにすることで、マーケティング上の問題の具体的な解決策の提示や、新たなターゲット・ニーズの探求に有効です。

定量調査と定性調査の違いとは
定量調査はその成果が「数値」で示される調査方式です。これは大量の人々に対して行われ、その反応や意見、行動を数字で計測し、傾向やパターン、関連性を分析するのに適しています。結果は パーセンテージ形式で示され、「”はい” と答えた人の数は○%、”いいえ”と答えた人の数は△%」や「”重要”と回答した人の数は□%」といった表現が使われます。分析では比較、相関、回帰などの統計手法が用いられます。
一方、定性調査は「言葉」を中心にした調査で、より詳細で深い情報が得られます。対話、インタビュー、観察などを通じて、数値化できない主観的な情報や感情、思考、行動の背景を探ります。得られた情報はテキストや画像などの非数値データとして分析され、主に言語分析やテーマ分析が用いられます。
調査目的の違い
定量調査と定性調査は、調査分析のための基本的な二つのアプローチです。
定量調査は量に焦点を当て、数値データの収集と分析を行います。逆に、定性調査は調査対象の「質」に照準を当て、因果関係やベースラインの理由を掘り下げて理解します。
見方を変えて考えると、定量調査は証明された仮説の関連度や影響度、範囲を確認や認識をします。一方、定性調査は新たな視野や問題を生成するための洞察の源となります。
これら二つの使い分けは「何を理解したいか」によって決まり、理想的な研究では両者がきちんと組み合わせられます。
商品開発の市場調査を例にとると、新商品の需要予想や販売予測などの定量的な情報が必要ですが、消費者の購買意欲や商品への反応・フィードバックなど定性的な情報もまた重要です。
定量調査と定性調査を目的に合わせ、組み合わせることでより適確で実用的な調査結果を生み出せます。
定量調査のメリット・デメリットとは
定量調査の強みとして挙げられるのは、その客観性と、大量データを扱いやすいことです。数値を用いることで主観的な解釈が最小限に留められ、その結果として得られる情報は誰が見ても同じ意味を持ちます。また、データ量が多ければ多いほど分析の精度も上がり、さまざまな仮説の検証に役立ちます。
また、アンケートなどをWeb上で行えば、手間や費用も抑制できるというメリットもあります。しかし、重要なのは数値化されたデータを適切に解釈し、企業の戦略や意思決定へと反映させることです。例えば、商品の購入率に男女差が5%あるとしたら、その5%の違いがどの程度の意味を持つのか、といった分析力が求められます。
定量調査の弱点としては、質問を設計する際にまだ予測できない様々な回答や意見を引き出しにくいことが挙げられます。あらかじめ設定した選択肢以外の情報を取得することは難しいという制約があります。

定性調査のメリット・デメリットとは
IoTの普及やビッグデータ利用の増加に伴い、一見ただの数字に見える消費者の行動データを詳細に集積することは容易になりました。しかし、これらの数字だけでは物語ることのできない背景情報を把握し、効果的なビジネス戦略を策定するためには、定性調査が必要不可欠です。
定性調査にはいくつかの課題も存在します。まず、調査対象者が実際に調査が求めるデータを充実して持っているかを事前に判断することが難しいため、适合する対象者のセットアップは困難です。また、定性データは数値化することができないため、データ分析の過程で調査者の主観が色濃く影響する可能性があります。
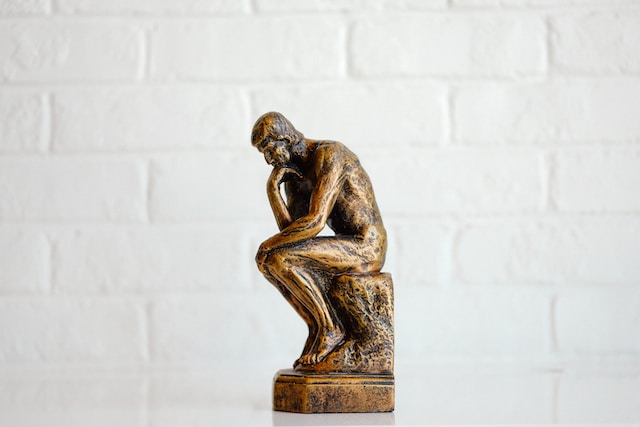
定量調査の方法とは
定量調査の方法はいくつかあります。代表的な調査方法をご紹介します。
インターネットリサーチ
定量調査の中でもたいへん便利で、効率的にデータを収集できる方法として、「インターネットリサーチ」が浸透しています。インターネットリサーチでは、Web上で稼働するアンケートを使って、多種多様な属性を持つ利用者から情報を得ます。
特筆すべき利点として、幅広い参加者から大規模なデータを迅速かつコスト効率良く得られること、そして調査の内容によってアンケートの質問や表示方法を適宜調整できる点が挙げられます。
インターネットリサーチは回答者の偏りや回答の信頼性などに取り組む必要があります。調査対象の性質をしっかり把握し、適切なサンプル設計や質問内容を設定することが重要となります。
会場調査(CLT)
会場調査(CLT:Central Location Testing)は、消費者に特定の場所で商品やサービスを体験させ、その評価や比較を行う調査方法の一つです。主にショッピングモールや会議場のような人々が集まる場所で行われます。
この調査は、新たに提供される商品を投入前に実際の消費者の反応を確認するためや、新旧の商品の違いを明らかにするために採用されます。テイスティングイベントなどにおいて、商品を直接試すことで具体的な反応を取得することができ、市場への投入を正確に判断する助けとなります。
会場選びや参加者の調整といった事前準備には時間と費用がかかることが課題です。また調査地の範囲が狭いため、地域性が結果に影響を及ぼすこともあります。

ホームユーステスト
「ホームユーステスト」という方法は、新商品やサービスの性能や満足度を測る重要な定量調査手法です。これは、主に健康食品やスキンケア商品など、一定期間利用しないと効果が実感できないアイテムを対象に行われます。研究会社は、選ばれた被験者に製品とその使用方法、そして評価シートを送付し、指定期間製品を使ってもらいます。
このテストは開発初期のユーザー反応を深く把握する素晴らしい手法です。後の製品改良やマーケティング戦略立案に活かすことができるでしょう。
郵送調査
「郵送調査」は、アンケート用紙を対象者の自宅やオフィスまで直接送付し、記入されたものを再び郵送で受け取るという調査法です。この方法の大きな特徴はプレッシャーを感じることなく、自分のタイミングで回答できる点で、これにより詳細な情報を取り出すことが可能となります。
また、この方法は広範なデータ収集を比較的経済的なコストで実現可能で、さらにはネット環境が整っていない層や、携帯電話の利用が少ない人々からも意見を引き出すことが可能です。然し、反応率の低さや偏向、そして回答までの時間が長くなることが問題となる点は十分留意が必要です。

定性調査の方法とは
定性調査の代表的な方法も確認しておきましょう。
グループインタビュー
グループインタビューとは、特定のテーマや問いに対し、複数の人々が共に討議する形式です。進行役のモデレーターが設定するテーマに基づき、集まった人々の意見や視点の違いを探るだけでなく、参加者間の交流を通じて新たな視点を見出すことも可能です。
行き届いた運営がされたグループインタビューは、一対一のインタビューと比べて、多様な情報を手に入れることができます。それは、全員が同じテーマについてそれぞれ異なる視点から考察し、多面的に討議するからです。グループインタビューは、新商品の構想、ニーズの把握、ブランドイメージの調査など、さまざまなシチュエーションでの有用性を証明しています。
デプスインタビュー
「デプスインタビュー」とは、調査者と対象者が一対一のインタビュー形式で行う深く掘り下げる手法です。実際の会話や回答の流れに沿って、質問内容をアジャストしたり追加したりすることが可能で、丁寧に心理分析を行いながら対象者の本音や意思を明らかにします。
この手法には30分程度の時間を要しますが、深層心理に迫ることが可能となり、グループインタビューよりも直接的で率直な意見を得ることができます。ただし、この方法では量的なデータ収集が目的ではなく、質問の設定や配列の微調整が求められるため、インタビュアーのスキルが重要となります。
行動観察調査(オブザベーション調査)
行動観察調査は、具体的な商品やサービス、あるいはイベントなどに対する消費者の行動を、現場で確認する調査法になります。具体的には、消費者が商品を買うときやサービスを使うときなどに調査者が同行してその一部始終を観察するというものです。
例えば、数々の洗濯洗剤が存在する市場で、消費者がどの洗剤を選び、何に取り組んで決定しているかを観察することです。こうして観察を続けることで、消費者が自覚していない、あるいは自覚はしていても口にするまでに至らないような潜在的な意識について発見することが可能になるのです。
訪問観察調査(家庭訪問)
訪問観察調査とは、実際の生活環境に足を運んで質的データを集める調査方法の一つです。特に家庭訪問を採ることで、あらゆる角度からその生活の実情を捉えることができます。具体的には、実際に目の当たりにした状況・様々な行動や表情を通じて、利用者の価値観や感情、生活スタイルを理解することを目指します。
この方策は、家庭内で実際に使用されている製品やサービス、関係者の態度や規則性、家族内の人間関係などを直接観察することが可能です。無造作な状態から、家庭ごとの思想や行動判断を読み解くことも可能になります。

定量調査と定性調査の使い分けとは
調柔の種類の適切な使い分けは、明確な目的設定が求められます。
調査を行う目的が具体的に決まっているか、データを用いてどのような分析を経て何を解決したいのか、これらがクリアになっているかが調査設計の鍵となります。
例えば、調査目的が「仮説の検証」、「現状やトレンドの把握」、「結果の数値による裏付け」、「範囲や数量の比較」などであるときは、その目的を達成するためには定量調査が最適だと言えます。
逆に、「新たな仮説の立案」、「詳細な背景や原因の探求」、「行動に至る心理や価値観の理解」などが目的であれば、これらを深く掘り下げるためには定性調査が適しています。

まとめ
定量調査は数値データに基づく、定性調査は意見や感情に焦点を当てた調査手法です。
前者は大規模な調査に必要で、統計分析やトレンド把握に有効です。後者は思考や行動の深層を探る際に有用で商品開発や改善策立案に役立ちます。
使い分けの知識で業務の質が変わる可能性がありますので、違いを理解しておくことが重要です。
よくある質問

定性調査と定量調査の違いは何ですか?
定量調査はデータを数値化し、統計的に分析するために設計された調査方法です。一方、定性調査は、対象者の言葉や行動、または観察者の記述に基づく生の情報を収集し、数値化できないデータを扱います。
定量調査のデメリットは?
定量調査のデメリットは以下の通りです。
質問の設計や表現によって、回答が影響を受けることがある。
数字の分析能力が必要でないと、データから得られる重要な洞察を見逃すことがある。
定量的調査手法とは?
定量的調査手法とは、数値化可能なデータを集め、それを分析する調査手法です。
主に選択式のアンケート調査を指し、特定の選択肢がどれだけの割合で選ばれたかを分析します。定量調査の代表的手法には、ネットリサーチや会場調査、ホームユーステストなどがあります。
定性調査と定量調査の順番は?
「定性調査 → 定量調査」の順番では、まず定性調査で仮説を構築し、その後に定量調査でその仮説を検証します。
定性調査は市場構造やターゲットの特性を把握するために有効であり、仮説を導くための情報収集に役立ちます。
それに対して、定量調査は得られた仮説や仮定を数値化し、統計的な手法で検証する手段として利用されます。
定量調査の特徴は?
定量調査の特徴は、結果を数値化できることです。数値データとして得られるため、説得力のあるデータを取得できます。
統計的な分析が可能なため、需要予測の正確性や仮説検証の確実性が高まります。特に、オンラインでのアンケートでは調査費用が比較的低く抑えられ、手軽に実施できる利点があります。
定性調査でわかることは何ですか?
定性調査の特徴は、ユーザーが「はい/いいえ」では答えられないような情報を詳細に収集できることです。
変容性のある情報、具体的な行動の理由や根拠、経緯などを理解することができます。例えば、1対1の会話形式では、対象者の意見だけでなく、その意見に至った背景や理由を探ることができます。
アンケートとヒアリングの違いは何ですか?
アンケートとヒアリングの相違点は、アンケートが定量調査に該当し、ヒアリングが定性調査に該当する点です。
アンケートは数値化可能な情報を集めることが目的で、調査項目には満足度やおすすめ度などが含まれます。 対照的に、ヒアリングでは数値化が難しい行動の理由や背景など、定量的に表現しづらい情報を収集します。
定性調査の費用はいくらですか?
定性調査の費用は幅広く変動します。
調査手法や実施内容、対象者数によって大きく異なります。一般的な目安としては、10万円から300万円程度がかかることがあります。
ただし、定性調査も様々な種類があり、その中でどの手法を使用するかによって費用が異なることを覚えておくと良いでしょう。
定性調査のサンプル数は?
定性調査では、一般的にサンプル数は比較的少ない傾向があります。インタビューなどの対象者は、多くても100人未満であり、10人前後で実施されることもあります。
サンプル数が少なくても、得られた情報から「心理的な共通項」を見つけ出し、商品開発やマーケティング戦略に有益な洞察を得ることができます。























