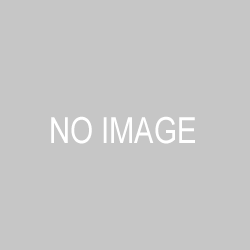グリーントランスフォーメーション(GX)とは?DX・SXとの違い
GX(グリーントランスフォーメーション)は、21世紀のビジネスにおいてますます重要な概念となっています。
このアプローチは、従来のエネルギー源から再生可能エネルギーへの移行を中心に、企業や社会のシステムを環境にやさしいものへと変革することを目指しています。本記事では、GXがなぜ注目されているのか、その背景や特徴に迫ります。

GX(グリーントランスフォーメーション)とは
GX(グリーントランスフォーメーション)という新概念が、企業によるサステナビリティへの取り組みを示す象徴的な用語となっています。
これは、企業が社会とともに発展し、持続可能性を求める社会の形成を目指し、それを実現する為の経営戦略や事業展開を考える概念です。GXの真髄は、環境に配慮した取り組みが企業の競争力を強化するという二面性にあります。
企業の責務としてGXを位置づけ、全組織の関与で取り組むべき課題とすることが強調されています。
それを可能にするためには、経営の透明性の確保や情報の開示という形での強化、更には企業統治という形のガバナンスの改革や、関係者との接点を持つコミュニケーションが求められています。

DXとは
DX、つまりデジタルトランスフォーメーションは、業務を革新し経営を変える活動であり、その本質は単なる業務効率化だけにとどまらず、新規ビジネスの創出や競争優位性向上にも寄与します。
具体的にはAIやビッグデータを用いて顧客行動を分析し、個々の消費者のニーズに合致した商品やサービスを提供するなどの新しいビジネスモデルが考えられます。
さらに、クラウドコンピューティングやIoTを駆使し、上流から下流まで業務フローを改革することで業務効率化も追求します。
しかしDXの道のりは容易ではありません。新技術の導入、人間の業務を機械が代替するべきかどうか、そしてそれらが社会に及ぼす影響など、多岐に渡る課題が存在します。これらの解決が命題となっています。
DXは単なるテクノロジーだけではなく、組織全体の思考の転換も必要とする革新活動です。これはDXがGX、つまりエネルギーの変革と密接に関わる一環であるということを示しています。
自社のエネルギー利用を优化するためにも、事前にDXを達成する必要があります。その一環として、業務改革や残業の削減など、デジタル技術を用いた効率化が必須です。
GXとDXは一見別々の取り組みのように見えますが、GXの進行にはDXの達成が必須となるわけです。
SXとは
SXは「サステナビリティ・トランスフォーメーション」を指し、企業経営においてサステナビリティを重視する考え方です。
この概念は、経済産業省が設置した「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会」で提唱され、以来注目を集めています。
SXの主な目的は、企業のサステナビリティ(企業のビジネスの持続性)と社会のサステナビリティを調和させ、これによって企業の価値を向上させることにあります。
SXに取り組むことで、企業はブランディングやESG投資家からの高い評価を得るメリットがあります。

DX・GX・SXの関係性とは
DX・GX・SXは、すべて企業価値の向上に寄与します。
- DX: デジタル化を通じて企業の競争力を向上させる
- GX: 環境問題への貢献を通じて企業の成長を促進する
- SX: 社会の持続可能性を目指しつつ企業も継続する
これらのアプローチはお互いに関連しています。例えば、GXの一環として再生可能エネルギーを導入する場合、これは社会の持続可能性、すなわちSXに寄与します。
同様に、DXが解決する課題が社会的課題と結びつくこともあり、これらの取り組みはお互いに連動し、共通の目標である企業価値の向上に寄与しています。
GXとカーボンニュートラルとの違いとは
GX(グリーントランスフォーメーション)とは、地球温暖化や環境破壊、気候変動などを引き起こす温室効果ガスの排出を削減し、環境改善と共に経済社会システムの改革を行う対策です。
世界中の企業がこの対策に取り組んでおり、経済産業省も2050年までに温室効果ガスの排出量を0にするカーボンニュートラルを目指しています。
GXとカーボンニュートラルは、それぞれ異なる概念であり、目的も異なります。
カーボンニュートラルは、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指す取り組みです。
これは、排出が避けられない場合でも、吸収手段(例: 森林保全活動)を通じて排出量を相殺し、ネット(正味)ゼロの状態を追求するものです。目的は環境問題の解決と持続可能な社会の構築です。
一方、GXの目的は、環境問題の解決と同時に経済成長を促進することです。

GXが注目される理由とは
GXが注目されている理由について、詳しく見ていきましょう。
GXが注目される理由とは:地球温暖化による気候変化
気候変動に伴う地球温暖化が進行する中で、大規模な水害や森林火災などの自然災害が増加していることが、GXが注目される理由の1つです。
環境省の予測によれば、有効な対策が講じられないまま地球温暖化が進むと、2000年頃からの平均気温が最大で4.8℃上昇する可能性があります。これにより、自然災害が増加すれば、それに伴う経済損失が拡大し、人々の生活や自然体系にも深刻な影響が及ぶでしょう。
GXは、こうしたリスクを回避し、気候変動による影響を軽減するための取り組みとして注目されています。

GXが注目される理由とは:ESG投資の市場拡大
ESG投資は、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)の3つの側面を投資判断の基準に採用する思考様式です。
2020年には、世界のESG投資総額は約3,900兆円で、全体の35.9%を占め、今後さらなる拡大が予想されます。
ESGを無視した経営は、企業の評価低下や株価下落といったリスクを孕んでいます。その結果、ESGに深い関わりを持つGXは注目を集めています。
GXが注目される理由とは:カーボンニュートラル宣言
新たな注目ワードである「GX」が、カーボンニュートラルという概念の実現に大きな貢献をしています。
カーボンニュートラルとは何かと言うと、環境省の定義によれば、「人間の活動による温室効果ガス(GHG)の排出量と、自然環境(例えば森林など)によるGHGの吸収量をバランスさせ、結果的にGHGの排出をゼロにするための取り組み」を指します。
これは単にGHGの排出量をゼロにするのではなく、排出源からの排出と自然環境による吸収を調節して全体的な排出量をゼロに目指すものなのです。
カーボンニュートラルの実現に向けては、現在のGHGの排出量を削減し、一方でGHGの吸収を強化する努力が求められます。そして、ここで「GX」の登場です。GXは、エネルギーの消費と供給を早見することで、GHGの排出を抑制する技術として高い関連性を持っています。
企業や地方自治体からのカーボンニュートラル宣言が増える中、GXの導入や活用が深まることで、その実現への道筋が描かれてきています。
間違いなく、GXは温室効果ガス排出削減の新たなチャレンジとして、今後ますます注目を浴びるでしょう。
現時点ではGXが十分に展開されているとは言えませんが、先鋭的な展開や成功事例が明らかにされており、GXの可能性と期待は今後も増していくことでしょう。

GX推進に向けた政府の取り組みとは
2022年以降、日本政府は「GX実行会議」を継続的に開催し、有識者との協議を通じて具体的な施策の検討を進めています。同時に、経済産業省はGXに参加する企業グループが官・学・金と連携するための実践的なプラットフォームとして、「GXリーグ」を2022年に発足させ、2023年4月から本格的な活動を開始しました。
GX実行会議(岸田内閣)
新たな経済成長の推進策「GX(成長総力戦・Growth X)」が、日本政府から提示されています。これは人材、地域、産業の3つを主要な視点に据え、共同で持続的な成長を促す政策です。
この政策の実現を主導する「GX実行会議」は、安倍内閣からスタートし、現在は岸田内閣が引き継いでいます。各部門間の情報共有や協力体制の強化を通じて、日本の経済活性化に向けた具体的な施策を策定・推進しています。
この会議では、人材能力向上と技術革新を後押しする研究開発援助、地方の再生を促進する地域活性化策などが進められています。さらに、持続可能性を重視した環境・エネルギー政策や、新市場進出の支援などを含む産業競争力強化策も展開されています。
2022年7月以降、定期的に開催されている「GX実行会議」では、エネルギー供給の再編、成長志向型カーボンプライシングなどの施策、10年先を見据えた展望、世界各国の投資支援状況などが話し合われました。特に2023年8月の第7回会議では、GX経済移行債(トランジションボンド)やカーボンプライシングに関する具体的な案件に焦点を当てた討議がなされました。
このような一連の活動を通じて、「GX推進」は日本全体が一体となり、政府の指導のもと新たな経済成長を実現する取り組みとなっています。現岸田内閣の下、これらの施策とその効果に注目が集まっています。

GXリーグ(経済産業省)
GXリーグというのは、新しい産業の創出を目指す官民連携プロジェクトで、政府、学界、企業が結束し、最新のデジタル技術を用いて新たなビジネスを生み出すことにより日本の経済成長を促します。特にAI、ロボット技術、データ解析、IoTといった最先端のテクノロジーの利用を通じて、新たなサービスや商品の開発に取り組んでいます。
そのための具体的な施策として、GXリーグでは、企業の業種や規模に関係なく参加可能なGXプラットフォームの構築を進めています。このプラットフォームは新規ビジネスの提案や情報共有の場を提供し、多様な視点やアイデアの交換を促進します。
また、GXリーグはイノベーションを推進するため、新規事業の支援金やネットワーキングの機会も提供。企業だけでなく個人も参加でき、幅広い参加者の活動を促進しています。
これらの取り組みを通じて、GXリーグは新たなビジネスモデルを生み出し、経済と社会の好循環を目指しています。その成果は、社会全体への対価として評価され、参画者の成長につながることが期待されています。

GXを支える地域・くらしの脱炭素(環境省)
「GX(グリーン・エコ・エクスペリエンス)」の実現に向けた我々の目指す先進のビジョンは、環境と経済の両立です。このビジョンの実現に向けて、日本政府、特に環境省は、積極的に脱炭素化に取り組んでいます。
2050年カーボンニュートラルを見据えた環境省のアクションプランは、地域での脱炭素化を基盤に据えています。その一環として、地域脱炭素ロードマップおよび地球温暖化対策計画に基づき、2025年度までの集中対策期間には、少なくとも100か所の脱炭素先行地域の指定を進め、全国各地で重点対策を積極的に推進します。
注目すべきは、その実施策の一部として、住宅部門での脱炭素化にも取り組みが見られることです。具体的には、高性能な断熱窓への改修の推進や、建材と一体化した太陽光発電システムの開発を進め、新築および既存の建設物でのZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を拡大します。
我々が追求する持続可能な社会の形成、すなわちGXのビジョンの具現化には、地域の理解と協力が不可欠です。こうした取り組みを通じて、我々は一歩一歩、全国一丸となったサステナブルな未来に進む道筋を切り開きつつあります。

GX推進法とは
この章では、GX推進法について詳しく解説します。
GX経済移行債発行
政府は、150兆円を超えるGXへの投資を実現するため、2023年度から10年間で20兆円規模のGX経済移行債(脱炭素成長型経済構造移行債)の発行を計画しています。通常の環境債(グリーンボンド)は主に再生可能エネルギーへの投資に充てられますが、GX経済移行債(トランジションボンド)は高い炭素排出を持つ企業が脱炭素に向けて幅広い投資に活用できます。
この約20兆円の政府支援は、水素やアンモニアなどの次世代エネルギーの需要拡大支援や、製造業の産業構造改革、省エネの促進などに充てられる方針です。

GX推進機構設立
GX推進機構(脱炭素成長型経済構造移行推進機構)は、民間企業のGXへの投資支援や、化石燃料賦課金・特定事業者賦課金の徴収、排出量取引制度の運営などを担当する専門組織です。
また、GX技術の社会実装段階におけるリスク補完策(債務保証等)も含め、成長志向型カーボンプライシングの施策を一元的に実施します。
政府は、2026年度に予定している排出量取引制度の本格稼働を見据え、2024年度に推進機構を設立する予定です。

成長志向型カーボンプライシング導入
カーボンプライシングは、CO2排出への課税や売買取引を通じて価格付けを行うシステムのことを指します。既存の例としてはEUの排出量取引制度やイギリスの炭素課税があります。
しかし、単なる排出削減だけでなく、経済成長とのバランスも求められています。日本ではこの観点から、「成長志向型カーボンプライシング」の導入が検討されており、GX推進法という法律案が提出されています。これにより、環境に配慮する一方で、経済の成長も図ることができる仕組みが整備され、持続可能な社会の実現を目指します。
具体的には、先行投資を支援するためのGX経済移行債の活用や、投資のインセンティブを提供するGXリーグにおける排出量取引制度の運用などが期待されています。GX推進法の成立によって、日本における環境対策投資の取組みがますます活発化しています。
カーボン排出に対するコストが発生する制度や賦課金制度が徐々に引き上げられる方針が示されており、企業にとっては早めのコミットメントが求められます。今後のさらなる展開に注目が集まっています。

企業がGXに取り組むべき理由とは
GXについて、各国政府や投資家、消費者などの関心も高まっており、脱炭素に消極的であることは企業経営において重要なリスクとなりつつあります。ここでは、企業がGXに取り組むべき理由を詳しく探っていきます。
法・国際ルールにおける義務化の流れ
国際的な動きとして、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)が2017年に提出した提言が挙げられます。この提言は、気候変動に伴う「リスク」と「機会」の財務的影響を理解し、それを内部監査などの対象に組み込むことを目的としており、各国の企業に経営の持続可能性向上を奨励しています。2023年6月時点で、日本国内の1,300以上の企業・機関が賛同し、統合報告書や財務諸表を通じて非財務情報を積極的に開示しています。
また、日本国内では、エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)が2023年4月に改正され、非化石エネルギーに関する新たな要件が組み込まれました。一定規模以上の工場・事業場や運輸分野の事業者は、エネルギー使用状況を定期的に報告するとともに、非化石エネルギーへの転換に関する中長期計画を提出することが求められます。さらに、電力需給の状況に応じた「上げDR」(再エネ余剰時などに電力需要を増加させる)や「下げDR」(電力需給ひっ迫時に電力需要を抑制させる)の実績報告も義務化されています。

投資家が脱炭素に関心
企業が持続可能な成長を続けるためには、エコフレンドリーなグリーンエネルギー(GX)への誓約が決定的な要素となっています。企業が環境への意識を持つことはもちろん、その積極的なアクションが投資家によって注目され、評価されている時代を迎えています。これは何故なら、現代の投資家達は、企業が単に経済的な利益だけでなく、社会・環境に対する価値も生み出しているかを重視しているからです。
特に、地球温暖化問題が深刻化している今、投資家達は炭素排出量削減に本腰を入れる企業を強く支援しており、そうした企業への投資額も右肩上がりで増えています。社会全体が持続可能な明日を作り上げるためには、企業のGXの動きが欠かせません。また、企業のGXへの成果は、投資家の信用獲得、そして資金調達条件の改善にも寄与します。
日経ESGの「ESGブランド調査2022」によれば、機関投資家や個人投資家の5割以上が再生可能エネルギーの状況を見守っており、東京証券取引所のプライムリストの企業の炭素排出量削減のための債券発行も増えています。ESG債券を発行したことのある企業のアンケートでは、自社の取り組みが認識され、新規投資家の開拓につながるなどのメリットが明らかにされています。
さらに、経済産業省と東京証券取引所は共同でSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)銘柄を設け、持続対応力を強化する上場企業を選定し、投資家に対する吸引力が高い銘柄として公開し、GX投資のインセンティブを刺激しています。
消費者から選ばれる
企業がGXに取り組むべき理由は、環境省がGX実現に向けて、商品やエネルギーの需要側に広く働きかけている点にあります。環境省は国民・消費者の行動変容を促進し、新しいライフスタイルを提案するための国民運動「デコ活」を主導しています。
将来的には、脱炭素の取り組みがますます消費者に浸透するでしょう。この中で、環境負荷の少ない商品やサービスへの需要が拡大すると予想されます。従って、消費者に選ばれる企業となるためには、気候変動対策をコストではなく、ビジネスチャンスとして捉えることが非常に重要です。
環境に配慮し、社会的責任を果たす企業が積極的にGXに取り組むことで、消費者からの支持を得やすくなり、企業価値を高め、競争力を向上させることが期待されます。

まとめ
GXは温暖化対策や持続可能な発展の観点から、企業や国が取り組むべき重要な課題です。環境への影響を最小限に抑えつつ、新たなビジネスモデルの構築を可能にするGXは、今後ますます広がりを見せることでしょう。
企業がGXに取り組むことで、環境負荷の低減だけでなく、社会的な信頼性向上やビジネスの競争力向上にもつながる可能性があります。
よくある質問
カーボンニュートラルとGXはどう違うのですか?
GXとカーボンニュートラルの相違点は、GXが脱炭素社会を実現するための包括的な概念であり、産業構造や社会システムに変革をもたらそうとする一方で、カーボンニュートラルはその中で特定の施策として位置づけられるものです。つまり、これら2つはまったく別のものではなく、GXは脱炭素社会を達成するための総合的な取り組みであり、その中でカーボンニュートラルが特定の手法として位置づけられています。
脱炭素のGXとはどういう意味ですか?
脱炭素のGXとは、再生可能なクリーンエネルギーへの移行を促進し、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを指します。
これは、日本政府が掲げる2050年のカーボンニュートラル実現に向けて不可欠な施策の一環であり、政府は社会全体の脱炭素化を推進するためにGXを重要な投資分野の一つと位置付けています。
エネルギーのGXとは?
エネルギーのGXは、再生可能なクリーンエネルギーへの移行を推進する取り組みを指します。これは、脱炭素社会の実現に向けた日本政府の重要な施策であり、2050年のカーボンニュートラル実現を目指す一環として、政府が社会全体の脱炭素化を促進するためにGXを重要な投資分野の一つに位置づけているものです。
GXの効果は?
GXの効果は、以下の点で期待されています。
環境への影響の低減:GXは、再生可能なクリーンエネルギーへの転換などを通じて、環境に対する負荷や影響を減少させます。これにより、地球温暖化や気候変動などの環境問題に対処する手段となります。
脱炭素社会の実現:GXは、石油や石炭などの化石燃料に依存せず、再生可能なエネルギー源を活用することで、脱炭素社会の実現を目指します。これが2050年のカーボンニュートラル実現に貢献します。
クリーンエネルギーの導入:GXにより、太陽光発電や風力発電などのクリーンエネルギーが促進され、持続可能なエネルギーの導入が進みます。これにより、エネルギーの持続可能性が向上します。
温室効果ガスの削減:GXは、温室効果ガスの排出を削減するための施策を含んでいます。これが気候変動への対策として効果を発揮します。
経済成長と雇用創出:クリーンエネルギーの導入や環境に配慮した取り組みが促進されることで、新たな産業が育成され、経済成長と雇用・所得の増加が期待されます。
GXと地球温暖化の関係は?
GX(グリーントランスフォーメーション)は、地球温暖化と深い関係があります。
温室効果ガス排出の削減:GXは、主に再生可能エネルギーの利用やクリーンテクノロジーの導入などを通じて、温室効果ガスの排出を削減することを目指しています。これは地球温暖化の主要な原因である温室効果ガスの影響を軽減する手段となります。
持続可能な経済社会の構築:GXは、環境問題への対処だけでなく、経済社会システム全体の改革を目指しています。再生可能エネルギーの普及や環境に配慮したビジネスモデルの推進は、持続可能な経済社会の構築に寄与します。
企業のカーボンニュートラル実現:GXの一環として、企業は温室効果ガスの排出を抑制し、最終的にはカーボンニュートラル(排出ゼロ)を達成することを目指します。これは地球温暖化対策として極めて重要です。
総合的な気候変動対策:GXは気候変動への対策の一環として位置づけられており、温暖化や異常気象の抑制に寄与します。持続可能なエネルギー源の利用が進むことで、環境に優しい社会の構築が期待されます。