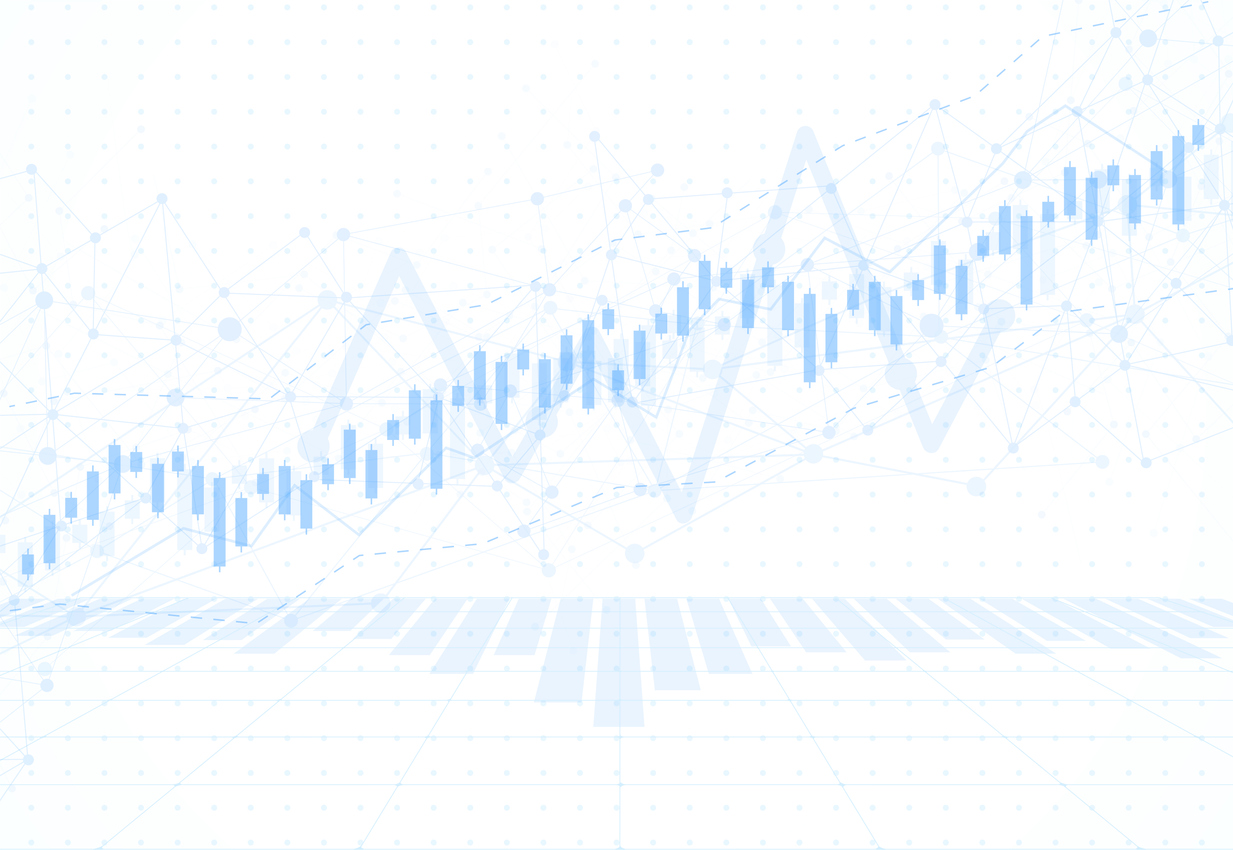小規模多機能型居宅介護看護とは?医療・介護の一体型サービスを徹底解説
小規模多機能型居宅介護看護(看多機)は、「通い」「泊まり」「訪問(介護・看護)」の3つのサービスを柔軟に組み合わせて提供できる介護保険サービスです。医療ニーズの高い要介護者の在宅生活を24時間365日体制で支える特徴があり、2012年に創設されました。
目次
1. 看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の基礎知識
1.1. 看多機とは
看護小規模多機能型居宅介護(通称:看多機)は、介護保険サービスの中でも比較的新しい地域密着型サービスです。医療ニーズの高い要介護者の在宅生活を支えるため、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせた複合型サービスとして2012年に創設されました。
看多機の最大の特徴は、「通い」「泊まり」「訪問(介護・看護)」の3つのサービスを、利用者の状態や必要に応じて柔軟に組み合わせて提供できる点です。事業所には看護師が常駐しており、医療依存度の高い方でも安心して在宅生活を続けることができます。
1.2. サービス創設の背景と目的
看多機が創設された背景には、住み慣れた地域での生活継続を望む高齢者の増加があります。特に医療ニーズの高い要介護者は、従来の介護サービスだけでは在宅生活の継続が困難でした。
そこで、介護と医療の連携を強化し、24時間365日の支援体制を構築するため、看護小規模多機能型居宅介護が制度化されました。看護職と介護職が協働してケアを提供することで、医療処置が必要な方でも在宅での生活を実現できるようになりました。
1.3. 看多機の特徴と強み
看多機の強みは以下の点にあります。
まず、一つの事業所で介護と看護の両方のサービスが受けられることです。利用者は複数の事業所と契約する必要がなく、また職員間の情報共有もスムーズに行えます。
次に、登録された利用者の状態に応じて、柔軟なサービス提供が可能です。通いを中心としながら、必要に応じて訪問や泊まりを組み合わせることで、その時々の医療・介護ニーズに対応できます。


2. 看多機と小多機の違いを徹底比較
2.1. 提供できるサービスの範囲
看多機と小規模多機能型居宅介護(小多機)は、一見似たようなサービスですが、重要な違いがあります。最も大きな違いは、訪問看護の提供体制です。
小多機では訪問看護は別途契約が必要ですが、看多機では訪問看護を含めたサービスをワンストップで提供できます。これにより、医療依存度の高い利用者でも、切れ目のないケアを受けることが可能です。
2.2. 医療ニーズへの対応力
看多機は看護師が常駐しているため、医療処置や急変時の対応が可能です。例えば、痰の吸引、経管栄養の管理、褥瘡の処置など、医療的なケアが必要な方でも対応できます。
一方、小多機では医療依存度の高い利用者の受け入れには制限があり、別途訪問看護との連携が必要となります。
2.3. 看護師の配置基準
看多機では、常勤換算で2.5人以上の看護職員の配置が義務付けられています。この基準により、24時間体制での看護サービス提供が可能となっています。
対して小多機では看護師の配置義務はなく、必要に応じて外部の訪問看護ステーションと連携する形を取ります。
2.4. 利用対象者の違い
看多機の主な利用対象者は、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ要介護者です。具体的には以下のような方々が対象となります。
・退院直後で医療的な管理が必要な方
・在宅での看取り期を希望される方
・医療処置が必要な方
・症状の急変リスクが高い方


3. 看多機のサービス内容詳細
3.1. 「通い」のサービス内容と特徴
通いサービスでは、看護師による健康管理や医療処置に加え、食事、入浴、機能訓練など、従来の介護サービスも提供されます。利用定員は登録定員29名に対し、通いは18名までと定められており、少人数でのケアが特徴です。
3.2. 「訪問看護」による医療的ケア
訪問看護では、医療処置やバイタルチェック、服薬管理などを行います。利用者の状態に応じて、必要な頻度で訪問看護を提供できる点が特徴です。医療機関の指示書に基づき、計画的な看護care提供が可能です。
3.3. 「訪問介護」でのサポート
訪問介護では、食事、排せつ、入浴などの身体介護や、調理、洗濯、掃除などの生活援助を提供します。看護職員と介護職員が密に連携することで、利用者の状態に応じた適切なケアを提供できます。
3.4. 「泊まり」の利用と30日ルール
泊まりサービスは、利用者の状態や家族の事情に応じて柔軟に利用できます。ただし、連続した宿泊は原則として30日までとされている点に注意が必要です。
3.5. 看取り期の対応
看多機では、医療機関や在宅療養支援診療所と連携しながら、看取り期のケアも提供可能です。住み慣れた環境での最期を希望する方とその家族を、医療と介護の両面からサポートします。


4. 看多機の利用条件と手続き
4.1. 要介護認定の要件
看護小規模多機能型居宅介護を利用するためには、まず要介護認定を受ける必要があります。要支援1・2から要介護1〜5までの認定を受けた方が対象となります。特に医療依存度が高く、訪問看護のニーズがある方に適したサービスです。
4.2. 医療依存度による判断
医療依存度の評価は、主治医の意見書や看護職員のアセスメントに基づいて行われます。以下のような状態の方が主な対象となります。
・医療処置(点滴、痰の吸引等)が必要な方
・重度の認知症で医療管理が必要な方
・終末期のケアが必要な方
・退院直後で医療的管理が必要な方
4.3. 利用開始までの流れ
利用開始までの手順は以下の通りです。
1. 要介護認定の申請と認定取得
2. 事業所の見学や相談
3. ケアマネジャーとの相談と計画作成
4. 利用契約の締結
5. サービス担当者会議の開催
6. ケアプランの作成とサービス開始
4.4. 併用できないサービス
看多機を利用する場合、以下のサービスとは併用できません。
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護
・短期入所生活介護
・他の地域密着型サービス

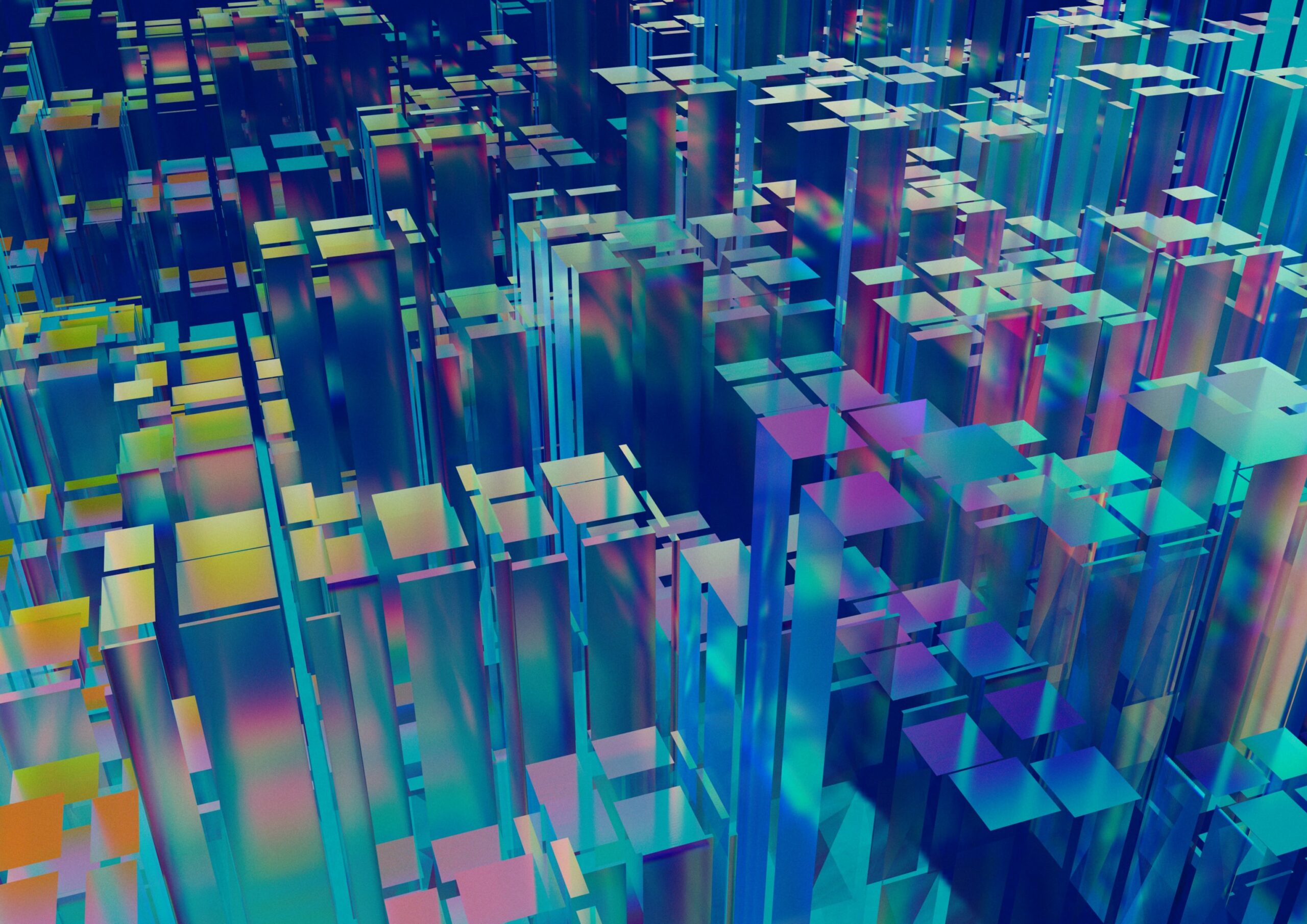
5. 看多機の運営体制
5.1. 事業所の人員基準
看多機の事業所には、以下の職員配置が義務付けられています。
・管理者:常勤専従1名
・看護職員:常勤換算2.5名以上
・介護職員:常勤換算で通いの利用者数が3またはその端数を増すごとに1名以上
・介護支援専門員:専従1名以上
5.2. 看護職員の役割と責任
看護職員は医療的ケアの中心的な役割を担います。主な責務には以下があります。
・利用者の健康状態の把握と管理
・医療処置の実施
・医療機関との連携
・介護職員への指導と助言
・緊急時の対応
5.3. 介護職員との連携
看護職員と介護職員の密接な連携が、看多機の特徴の一つです。日々のカンファレンスや記録の共有を通じて、利用者の状態変化に迅速に対応できる体制を整えています。
5.4. サテライト型事業所について
本体事業所から離れた地域でもサービスを提供できるよう、サテライト型事業所の設置が認められています。サテライト型事業所は本体事業所の支援を受けながら運営され、より多くの地域で看多機のサービスを利用できるようになっています。


6. 費用と利用料金の仕組み
6.1. 基本料金の構造
看多機の利用料金は、要介護度に応じた月額包括報酬制となっています。基本料金には「通い」「訪問」「泊まり」のすべてのサービスが含まれます。利用者負担は原則として1割(所得に応じて2割または3割)です。
6.2. 加算項目と金額
基本料金に加えて、以下のような加算があります。
・看取り介護加算
・総合マネジメント体制強化加算
・サービス提供体制強化加算
・認知症加算
6.3. 利用者負担の計算方法
月額の利用者負担は、基本料金と各種加算の合計額に利用者負担割合を乗じて計算します。この他に、食費や宿泊費は実費負担となります。
6.4. 医療保険との関係
看多機での訪問看護は介護保険でカバーされるため、別途医療保険を使用する必要はありません。ただし、医療機関での診療や処方箋による薬剤の費用は、通常通り医療保険が適用されます。


7. 看多機のメリット・デメリット
7.1. 利用者にとってのメリット
看多機の主なメリットは以下の通りです。
・医療と介護のワンストップサービス
・24時間365日の安心のケア体制
・なじみの職員による一貫したケア
・柔軟なサービス提供体制
7.2. 家族介護者への影響
家族介護者にとっては、以下のような利点があります。
・介護負担の軽減
・医療面での不安解消
・緊急時の対応への安心感
・レスパイトケアの活用
7.3. 注意すべき制限事項
以下の点には注意が必要です。
・他の介護サービスとの併用制限
・利用料金が比較的高額
・事業所数が限られている
・登録定員に制限がある
7.4. 選択時の判断ポイント
看多機の選択を検討する際は、以下の点を確認することが重要です。
・医療ニーズの程度
・家族の介護力
・経済的な負担能力
・事業所までの距離と通いやすさ
・24時間対応の必要性


8. 効果的な看多機の活用方法
8.1. ケアプランの立て方
効果的な看多機の活用には、適切なケアプランの作成が不可欠です。ケアプランは以下の点を考慮して作成されます。
・医療ニーズの程度と必要な医療処置
・日常生活における自立度
・家族の介護力と希望
・通い、訪問、泊まりの適切な組み合わせ
・リハビリテーションの必要性
8.2. 医療機関との連携
看多機における医療機関との連携は、以下の形で実施されます。
・主治医との定期的な情報共有
・訪問看護指示書の取得と更新
・急変時の連絡体制の確立
・退院時カンファレンスへの参加
・看取り期における連携強化
8.3. 家族との情報共有
利用者の在宅生活を支えるためには、家族との密接な情報共有が重要です。具体的には以下の方法で実施します。
・連絡ノートの活用
・定期的なカンファレンスの開催
・緊急時の連絡体制の確認
・医療的な注意点の説明
8.4. 緊急時の対応
看多機では、以下のような緊急時対応体制を整えています。
・24時間対応可能な連絡体制
・看護職員による随時の健康管理
・急変時の医療機関との連携
・緊急時の泊まりサービスの利用


9. 看多機の課題と今後の展望
9.1. 現場での課題
看多機が直面している主な課題には以下があります。
・看護職員の確保と定着
・医療依存度の高い利用者への対応
・介護職と看護職の連携強化
・サービス提供地域の限定性
・経営の安定性確保
9.2. 制度の方向性
看多機に関する制度は、以下のような方向性で進化しています。
・サテライト型事業所の促進
・看取り期への対応強化
・医療連携体制の充実
・人員配置基準の柔軟化
9.3. 地域包括ケアにおける役割
地域包括ケアシステムにおいて、看多機は以下のような役割を担っています。
・医療と介護の橋渡し役
・在宅療養支援の中核
・地域の看取り支援
・地域における医療・介護の連携推進
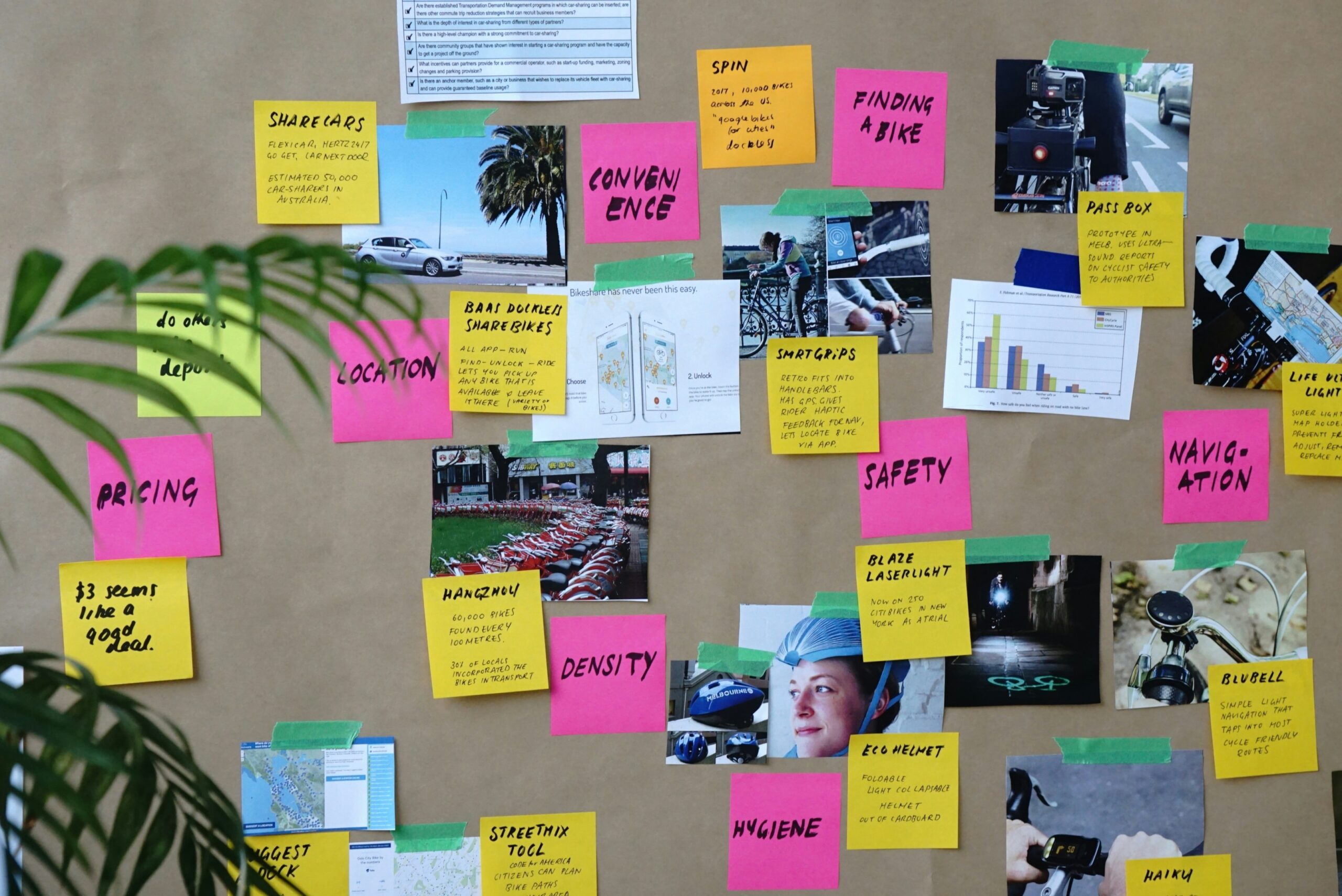

10. 実践的な利用検討ガイド
10.1. 事業所選びのポイント
看多機の事業所を選ぶ際は、以下の点をチェックします。
・看護職員の配置状況と経験
・医療機関との連携体制
・利用者の受入れ実績
・施設の立地と送迎範囲
・サービス提供時間と対応可能な医療処置
10.2. 見学・相談時の確認事項
事業所の見学・相談時には、以下の点を確認することが重要です。
・具体的な医療処置の対応可否
・看護職員の夜間対応体制
・利用料金の詳細
・送迎の可能範囲と時間
・緊急時の対応方針
10.3. 移行期の準備
看多機の利用開始に向けて、以下の準備が必要です。
・主治医との相談と情報共有
・必要な医療機器や衛生用品の準備
・家族間での役割分担の確認
・緊急連絡先リストの作成
・お試し利用の検討
10.4. 長期的な活用プラン
長期的な視点での活用には、以下の点を考慮します。
・医療依存度の変化への対応
・家族の介護負担の調整
・看取り期までの継続利用の検討
・定期的なケアプランの見直し
・地域資源との連携強化
また、サービスの継続利用に際しては、定期的なモニタリングと評価を行い、必要に応じてサービス内容を調整することが重要です。家族の状況変化や利用者の状態変化に応じて、柔軟にプランを見直していくことで、より効果的なサービス利用が可能となります。


よくある質問と回答
看多機と小多機はどう違いますか?
最大の違いは、訪問看護の提供体制です。看多機では訪問看護を含めた医療的ケアを一体的に提供できます。一方、小多機では訪問看護は別契約が必要です。また、看多機では看護師が常駐しているため、医療依存度の高い方でも受け入れが可能です。
訪問看護と看多機は併用できますか?
原則として併用はできません。看多機は包括的なサービスとして訪問看護も含まれているため、別途訪問看護を利用する必要はありません。ただし、特別な医療ニーズがある場合は、主治医の指示のもと例外的に併用が認められることがあります。
泊まりは連続して何日まで利用できますか?
原則として連続30日までの利用が可能です。ただし、利用者の状態や家族の事情により、柔軟な対応が行われることもあります。長期の利用が必要な場合は、事前に事業所と相談することが重要です。
看多機の利用にはどのような条件がありますか?
要支援1から要介護5までの認定を受けた方が対象です。特に医療依存度が高く、訪問看護のニーズがある方に適しています。また、事業所の登録定員や通いの定員に空きがあることも条件となります。
看取り期の対応は可能ですか?
看取り期の対応が可能です。医療機関や在宅療養支援診療所と連携しながら、24時間体制で支援を提供します。家族の希望や本人の意向を尊重しながら、住み慣れた環境での看取りをサポートします。居宅介護複合型サービスとは具体的にどのようなものですか?
複合型サービスは、介護事業所が提供する包括的なケアサービスです。通い・訪問・泊まりのサービスを組み合わせて、自宅での生活を総合的にサポートします。多機事業所として、利用者一人ひとりの生活機能に応じた柔軟なケアプランを提供します。介護福祉士を含む専門スタッフが24時間体制でサポートを行います。
型居宅介護の利用を検討する際の重要なポイントは?
居宅介護とは、住み慣れた自宅での生活継続を支援するサービスです。調査研究事業の結果によると、看多機事業を選ぶ際は以下の点が重要とされています: 1. 医療ニーズと介護ニーズの両方に対応できる体制があるか 2. 型居宅介護複合サービスとして、柔軟なサービス提供が可能か 3. 地域との連携体制が整っているか