
病院の経営が赤字にならない対策と戦略|医療経済実態調査から見る課題と解決策
病院の経営環境は、年々厳しさを増しています。医療経済実態調査によると、現在約65%の医療機関が赤字経営に直面しており、特に一般病院や民間病院における経営難が深刻化しています。その背景には、医療従事者の人件費増加、診療報酬改定の影響、新型コロナウイルス感染症による補助金の段階的縮小など、複数の要因が存在します。本記事では、最新の医療経済データと実例に基づき、病院経営における赤字対策、経営戦略の立て方、そして持続可能な経営のための具体的な施策について解説します。

医療経営の現状分析
医療経済実態調査から見る病院経営の実態
医療経済実態調査によると、2023年度において医療機関の経営状況は依然として厳しい状況が続いています。特に一般病院における経営の実態は深刻で、調査対象となった医療機関の約65%が赤字経営となっています。日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会の共同調査では、特に民間病院の経営難が顕著であることが明らかになりました。
病院の経営状況を詳しく見ると、人件費の増加が最も大きな課題となっています。医療従事者の確保が困難な状況下で、人件費は前年比で平均4.8%上昇。これは病院経営を圧迫する主要因の一つとなっています。また、設備投資の必要性も高まっており、医療機関の財務状況に大きな影響を与えています。
2024年度以降の医療機関の経営見通し
2024年度以降の病院経営は、さらに厳しい状況になることが予想されています。新型コロナウイルス感染症関連の補助金が段階的に縮小される中、多くの病院が経営の立て直しを迫られています。医療経済実態調査の分析によると、特に以下の要因が病院経営に影響を与えると考えられています。
第一に、診療報酬改定の影響です。2024年度の診療報酬改定において、医療機関の経営基盤強化に向けた取り組みが示されていますが、実質的な収益改善効果については不透明な部分が残されています。第二に、医療従事者の人件費上昇傾向が継続することです。働き方改革への対応も含め、人件費の増加は避けられない状況となっています。
赤字病院の割合と経営指標
現在、一般病院の中で経営が赤字になっている医療機関の割合は増加傾向にあります。特に地域医療を支える中小規模の病院において、その傾向が顕著です。医療法人の経営状況を見ると、利益率の低下が続いており、経営の持続可能性に課題を抱える施設が増加しています。
経営指標から見る赤字病院の特徴として、患者数の減少、病床利用率の低下、医業収益の伸び悩みなどが挙げられます。特に病院の経営状況を左右する要因として、以下の指標が重要とされています。


病院経営を圧迫する要因
医療従事者の人件費増加
医療従事者の人件費は、病院経営において最も大きな費用項目となっています。近年の医療従事者不足により、人材確保のための人件費の増加は経営を圧迫する主要因となっています。特に看護師や医療技術者の確保に関する競争が激化し、給与水準の上昇が避けられない状況となっています。
医療機関における人件費の課題は、単なる給与額の問題だけではありません。働き方改革への対応、夜勤体制の整備、有給休暇取得の推進など、労働環境の改善に関する費用も増加しています。これらは医療の質を維持する上で欠かせない要素でありながら、病院の経営を圧迫する要因となっています。
診療報酬改定の影響
診療報酬の改定は、病院経営に直接的な影響を与える重要な要素です。特に近年の改定では、医療機関の経営状況に大きな変化をもたらしています。医療経済実態調査によると、診療報酬の実質的なマイナス改定により、多くの病院が収益確保に苦心している状況が明らかになっています。
特に一般診療所と比較して、病院における診療報酬改定の影響は大きくなっています。入院医療の評価や人員配置基準の見直しなど、病院経営の根幹に関わる部分での変更が、経営の安定性を脅かしています。
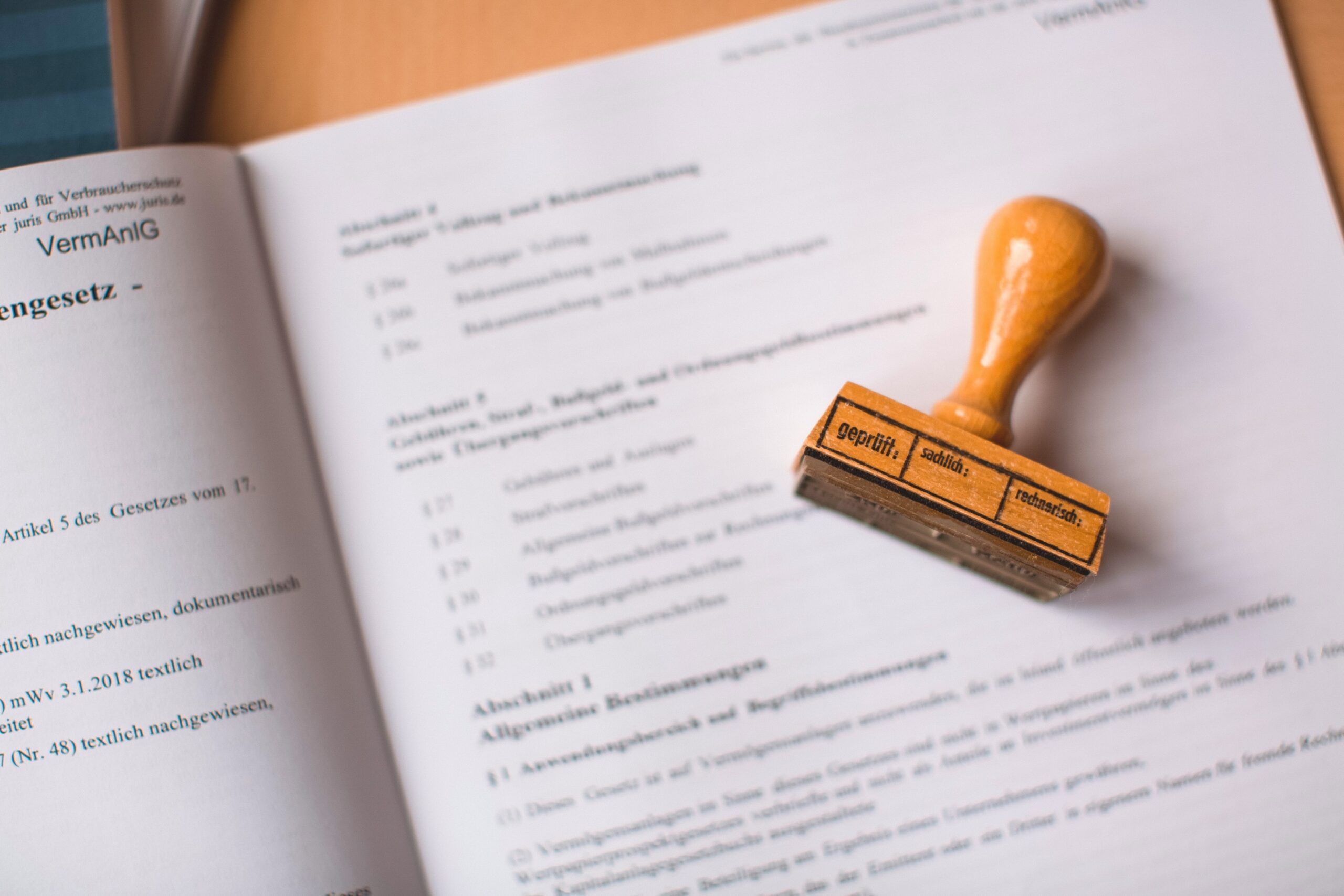
病床利用率の低下問題
病床利用率の低下は、病院経営における深刻な課題となっています。新型コロナウイルス感染症の影響により、一般病床の利用率が大きく低下し、医業収益に直接的な影響を与えています。特に民間病院において、この傾向が顕著に表れています。
病床利用率の低下は、固定費が高い病院経営において、即座に収益の悪化につながります。医療機関の経営者にとって、適切な病床管理と利用率の向上は、経営改善における重要な課題となっています。
新型コロナウイルスの影響と補助金
新型コロナウイルス感染症は、病院経営に多大な影響を与えています。感染症対応のための設備投資、人員配置の見直し、感染対策費用の増加など、様々な面で経営負担が増加しています。一方で、これまで提供されてきた補助金の段階的な縮小により、多くの医療機関が経営の転換点を迎えています。
特に感染症対応を行ってきた病院では、補助金収入の減少が経営に直接的な影響を与えています。医療法人の経営者は、アフターコロナを見据えた新たな経営戦略の構築を迫られています。
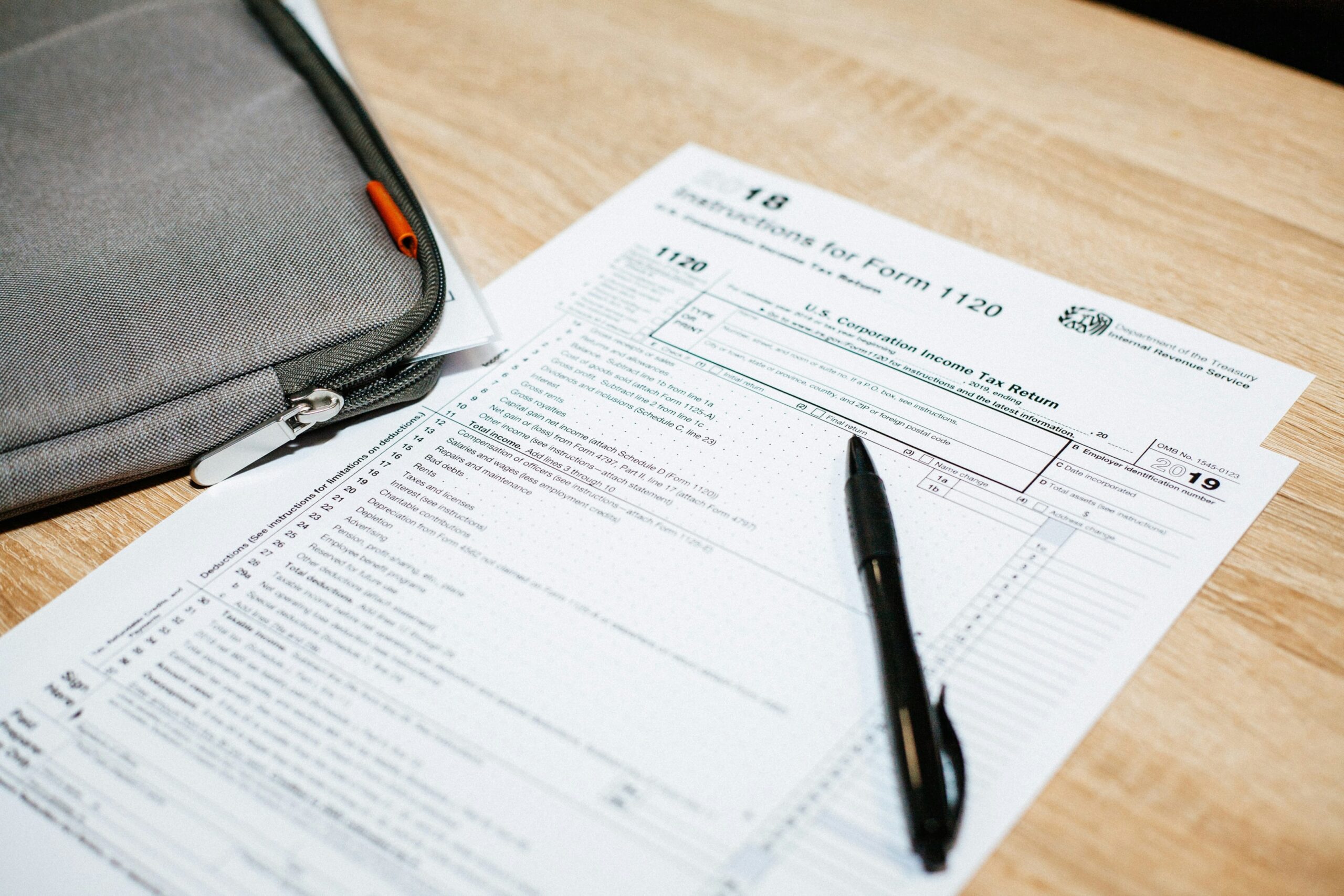

地域医療と病院経営の関係
地域医療構想と病院の役割
地域医療において、病院は欠かせない存在となっています。医療機関の経営状況は、地域医療の維持に直接的な影響を与えており、特に地方における医療従事者の確保や医療サービスの提供体制の維持が重要な課題となっています。医療経済実態調査によると、地域における中核病院の約40%が経営難に直面している現状があります。
地域医療構想の実現に向けて、病院経営の安定化は重要な要素となっています。特に一般病院における病床機能の分化・連携の推進や、医療法人の経営基盤強化が求められています。地域における医療提供体制の維持には、効率的な病院経営が不可欠です。

医療法人の活用と経営戦略
医療法人制度は、病院経営の安定化と効率化を図る上で重要な役割を果たしています。特に近年、医療機関の経営において、医療法人化による経営の効率化や、地域医療連携推進法人制度の活用が注目されています。経営戦略の観点から、以下の取り組みが重要とされています。
医療法人における経営の透明性向上と、ガバナンス体制の強化は、病院の経営基盤を強化する上で重要です。特に人件費の管理や設備投資の適正化において、医療法人としての組織的な意思決定が求められています。また、地域の医療機関との連携強化により、効率的な医療提供体制の構築を目指す動きも見られます。
公的病院と民間病院の違いと経営戦略
公的病院と民間病院では、経営環境や課題に大きな違いが存在します。公的病院は政策医療の担い手として重要な役割を果たす一方で、多くの病院が赤字に陥っている現状があります。一方、民間病院は経営の自由度が高い反面、競争環境の中で経営の効率化が強く求められています。
医療従事者の確保や人件費の管理において、公的病院と民間病院では異なるアプローチが必要となっています。特に民間病院における経営戦略では、医療の質の向上と経営効率化の両立が重要な課題となっています。

病院経営における経営改善策
経営データの活用と分析
病院経営の改善には、詳細な経営データの分析が欠かせません。医療機関における経営状況の把握と改善には、患者数の推移、診療科別の収益性、病床利用率などの指標を総合的に分析する必要があります。特に経営が赤字になるリスクの早期発見と対策には、データに基づく経営判断が重要です。
医療経済実態調査のデータを活用し、同規模の医療機関との比較分析を行うことで、自院の強みや課題を明確化することができます。また、診療報酬の算定状況や費用構造の分析により、収益改善の機会を見出すことが可能となります。
人件費の適正管理と業務効率化
病院経営において最大の費用項目である人件費の適正管理は、経営改善の重要なポイントとなります。医療従事者の適切な配置と業務効率化により、医療の質を維持しながら人件費の最適化を図ることが求められています。特に一般病院における人件費率の上昇は、経営を圧迫する大きな要因となっています。
業務効率化においては、ICTの活用や業務プロセスの見直しが効果的です。医療機関における業務の標準化や、タスクシフティングの推進により、医療従事者の負担軽減と効率的な人員配置が可能となります。


まとめ | 持続可能な病院経営のために
今後の病院経営の展望
医療機関を取り巻く環境は、今後も大きく変化していくことが予想されます。特に診療報酬改定や医療制度改革の影響により、病院経営はさらなる変革を求められています。持続可能な経営のためには、環境変化への柔軟な対応と、経営基盤の強化が不可欠です。
新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、多くの病院が経営戦略の見直しを進めています。特に医療法人における経営の多角化や、地域医療連携の強化など、新たな経営アプローチの重要性が高まっています。
経営者が今から取り組むべき施策
病院経営の改善に向けて、経営者は以下の施策に取り組む必要があります。第一に、経営データの詳細な分析と活用です。医療経済実態調査などの外部データも参考にしながら、自院の経営状況を正確に把握することが重要です。
第二に、医療従事者の確保と育成を含む人材戦略の強化です。人件費の適正管理と医療の質の向上の両立を図りながら、持続可能な経営基盤を構築することが求められています。また、地域医療における自院の役割を明確化し、それに基づいた経営戦略の策定と実行が不可欠です。

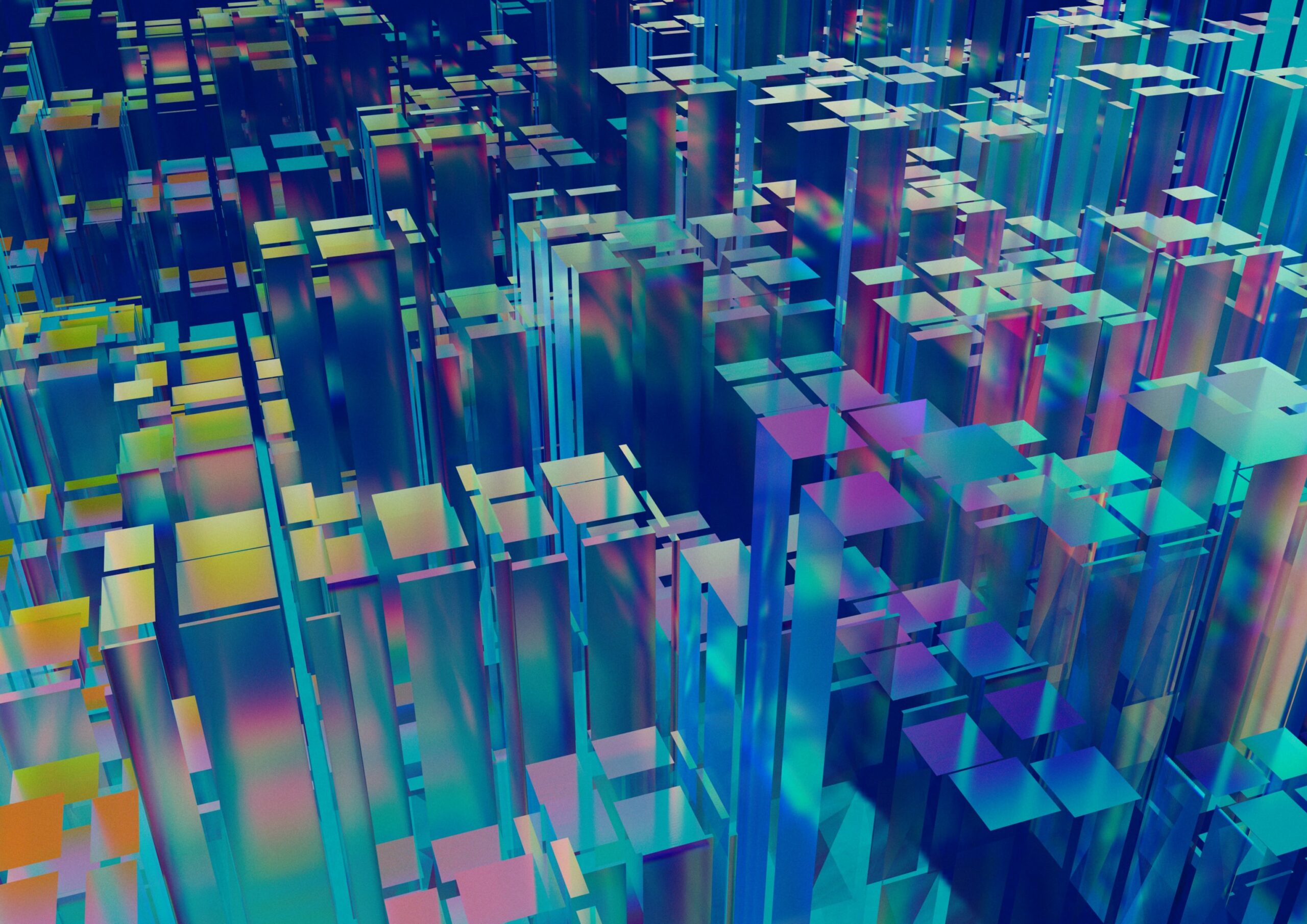
よくある質問と回答
病院はどうやって収益を上げているのですか?
病院の主な収益源は診療報酬です。入院診療、外来診療、手術、検査などの医療サービスに対して、診療報酬点数に基づいた収入を得ています。また、健診事業や介護事業など、診療以外の事業収入も重要な収益源となっています。医療機関の経営では、これらの収入源の適切なバランスを保つことが重要です。

病院が赤字になる主な理由は何ですか?
医療経済実態調査によると、病院が赤字になる主な理由として、人件費の増加、診療報酬のマイナス改定、患者数の減少、設備投資負担の増大が挙げられます。特に医療従事者の人件費は経営を圧迫する大きな要因となっており、多くの病院が経営難に直面している状況です。
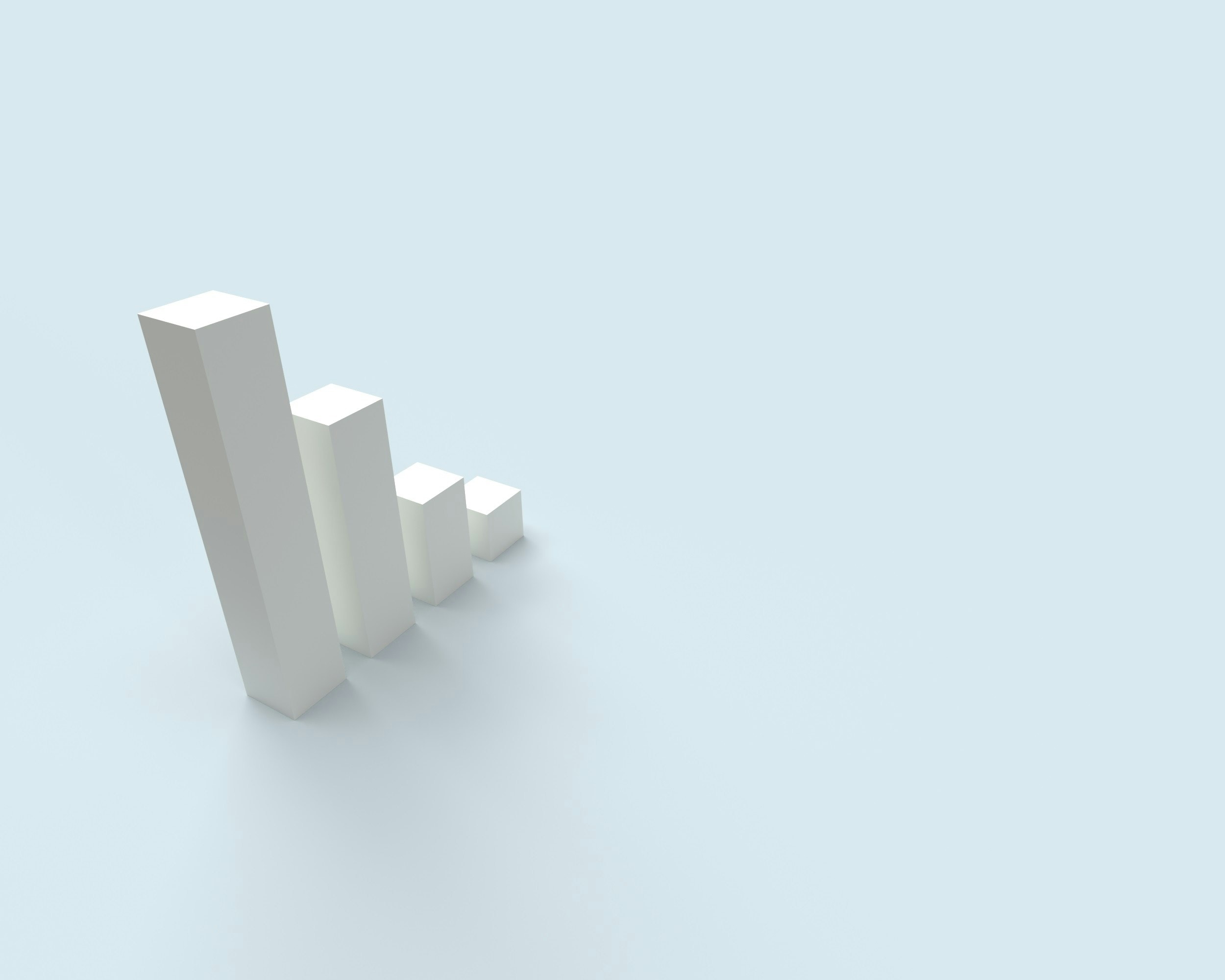
公的病院の赤字の原因は何ですか?
公的病院の赤字には、政策医療の提供による不採算部門の維持、救急医療体制の確保、へき地医療の提供などが影響しています。また、民間病院と比較して人件費水準が高く、意思決定の柔軟性が低いことも経営を圧迫する要因となっています。

医療経済実態調査とは何ですか?
医療経済実態調査は、厚生労働省が実施する医療機関の経営状況を把握するための調査です。病院、一般診療所、歯科診療所などを対象に、収支状況、職員給与、設備投資など、経営に関する詳細なデータを収集・分析しています。この調査結果は、診療報酬改定の基礎資料として活用されています。

潰れる病院の特徴とは何ですか?
経営破綻に至る病院には、患者数の継続的な減少、病床利用率の低下、人件費率の高騰、設備の老朽化、経営データの分析不足などの特徴が見られます。特に地域医療における役割が不明確な病院や、経営戦略の見直しが遅れている医療機関は、経営リスクが高まる傾向にあります。

開設者が考慮すべき経営リスクとは何ですか?
開設者は、医療費の変動リスク、人材確保・育成に関するリスク、設備投資に関するリスクなど、様々な経営リスクに注意を払う必要があります。特に、診療報酬改定や医療制度改革による収益への影響、医療従事者の人件費上昇などは、重要な検討事項となります。
























